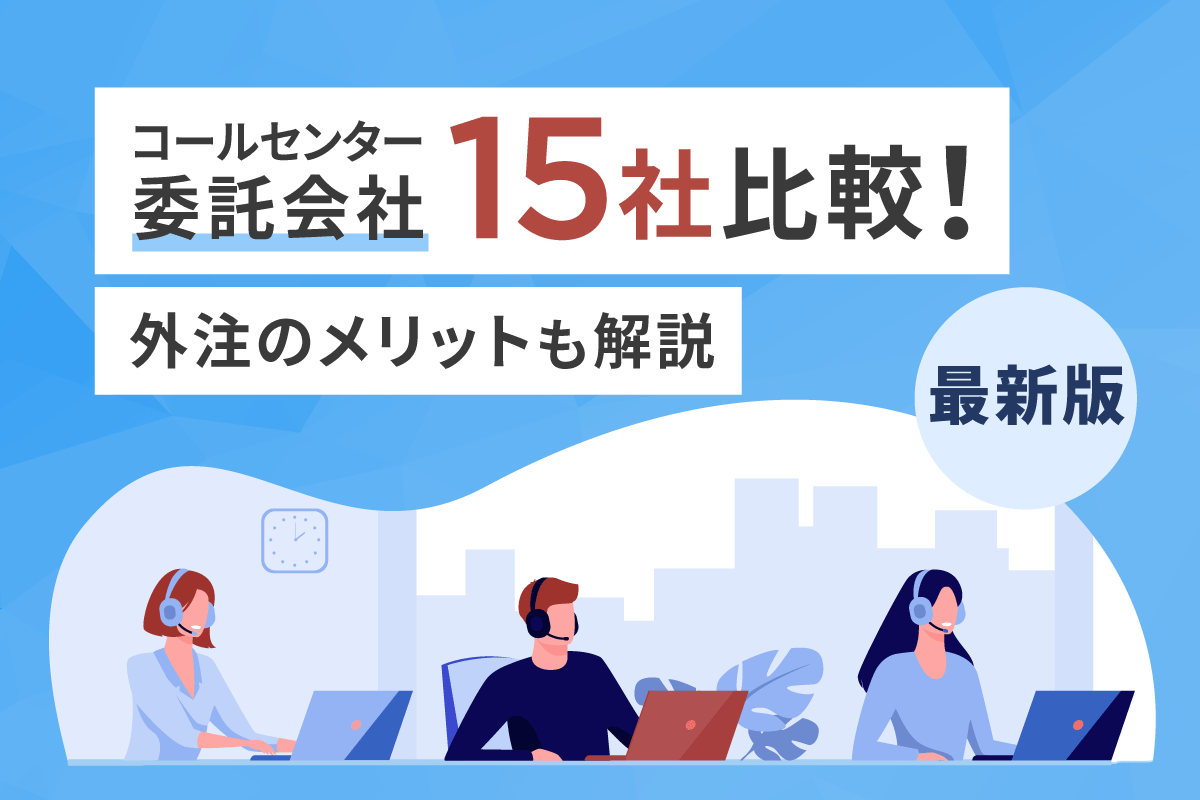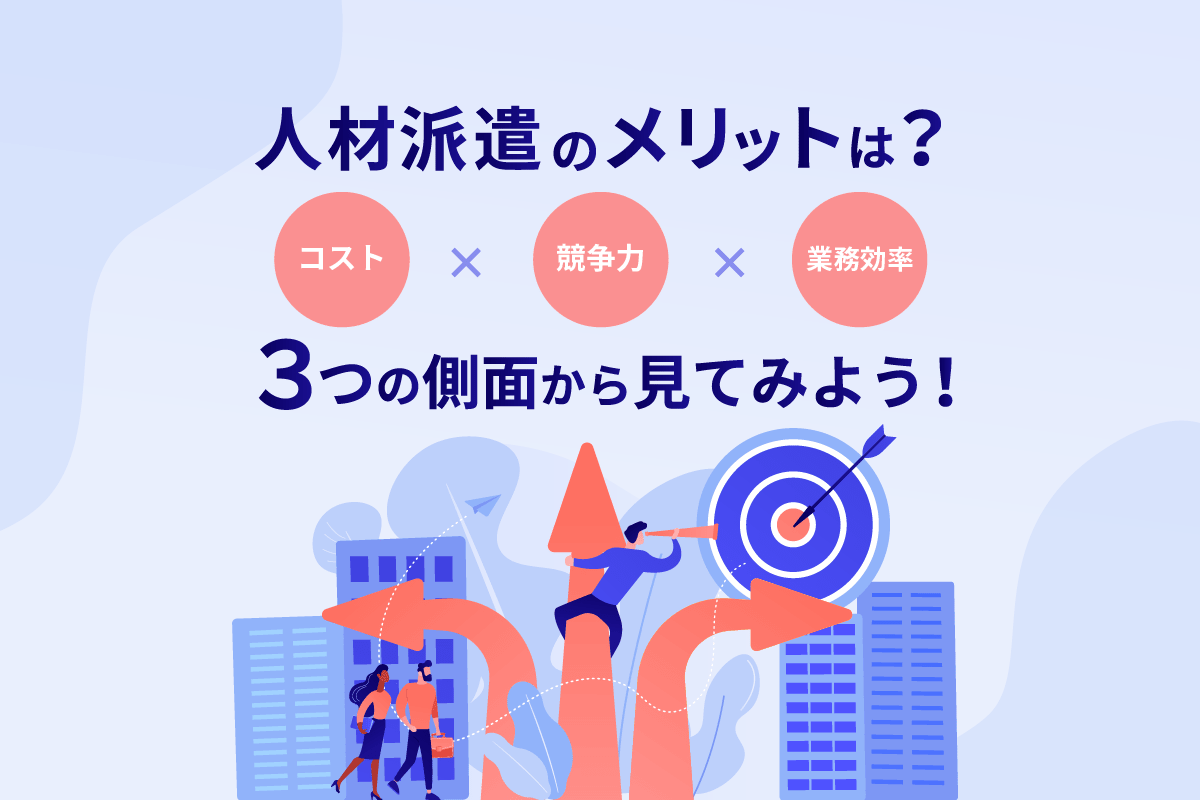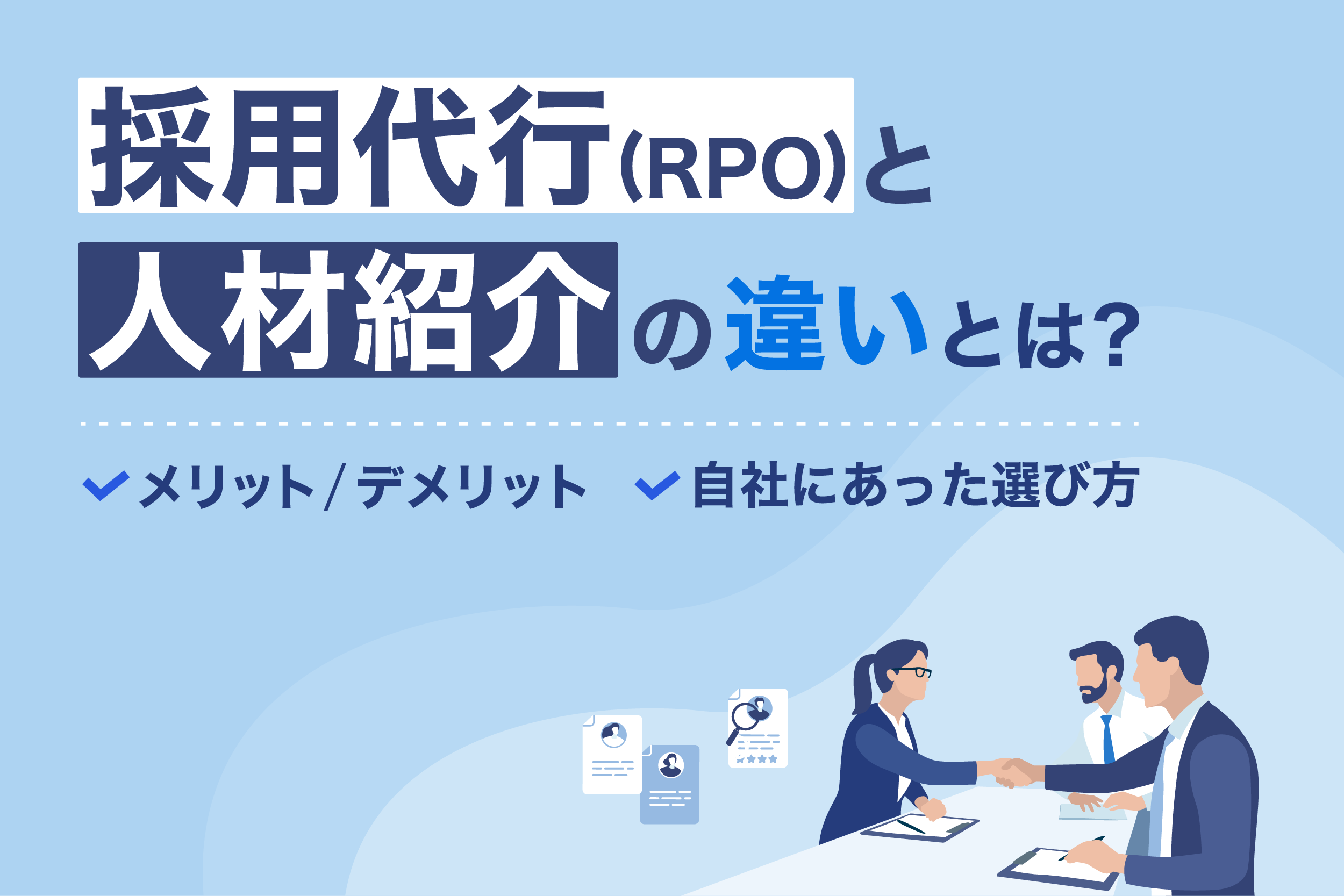「特定技能」の支援計画とは?必須10項目や実施方法を徹底解説
- 在留資格を知る
- 特定技能
2025/10/09

この記事でわかること
- 1号特定技能外国人支援計画の内容
- 支援計画の実施方法は主に2つ
- 登録支援機関への委託や内製化も可能
在留資格「特定技能」とは、人手不足が厳しい業界で一定程度の技能・知識を有する外国人に与える在留資格で、1号と2号があります。
特定技能1号とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人に与えられる在留資格です。
1号特定技能外国人を雇用するには、1号特定技能外国人支援計画が非常に重要となります。
支援計画を立てない場合、もしくは外国人への支援が不十分である場合、外国人の受け入れが不可となる可能性があるので、気をつけてください。
外国人雇用の悩まれていませんか?
雇用に向けて押さえておきたいポイントをまとめました
TOPICS
1号特定技能外国人支援計画とは
1号特定技能外国人の受け入れ機関は、外国人の日常や社会生活への支援義務が課せられています。
その支援計画は、1号特定技能外国人支援計画といいます。
特定技能外国人を実際に雇用する前に、この支援計画を必ず作成し出入国在留管理庁に提出するのが必要です。
計画の内容が不十分の場合、特定技能外国人の受け入れが許可されないこともあるので気を付けてください。
1号特定技能外国人支援計画の10義務支援項目
1号特定技能外国人支援計画に記載しないといけない義務支援項目は合計10項目あります。
各項目の内容について見ていきましょう。
1.入国前の生活ガイダンスの提供
日本での実際の生活状況やルールなどをオンラインミーティングツールを用いてガイダンスの提供を行います。
ガイダンスは3時間程度で、外国人が充分理解できる言語で行わなければなりません。
2.入国時の空港への出迎え及び帰国時の空港への見送り
空港という部分がポイントで、最寄り駅まで送迎すればいいということではありません。
空港まで迎えに行き、帰国の際も確実に自国に帰ることを空港で見届けることが重要です。
3.外国人の住宅の確保
住宅の確保とはいえ、家賃の負担まで必要なわけではなく、あくまで住宅を決めるまでのサポートのことです。
不動産会社の紹介はもちろん、必要に応じて内覧の同行をしてあげましょう。
保証人が必要なときなども協力することが必要です。
また、保証会社を通す際は、手数料の支払いについては受け入れ機関に負担を求められることがあります。
4.在留中の生活オリエンテーションの実施
具体的には銀行口座の開設や携帯電話の契約支援などを指します。
実際に必要な書類のサポートや窓口への案内はもちろん、事前にオリエンテーションを実施しましょう。
1番のガイダンスと同じく、オリエンテーションは外国人がもっとも理解できる言語で行うことが必要です。
オリエンテーションは8時間程度を目安に行います。
5.公的手続等への同行、各種行政手続についての情報提供と支援
国民健康保険や帰国後の納税に関する手続きのほか、居住地で必要な届出、受け入れ機関に必要な届出などの支援です。
どのような書類と届けが必要で、それぞれをどこで行えるかの情報を提供してあげましょう。
この場合も外国人が理解できる言語で行うことがポイントです。
6.生活のための日本語習得の支援
1号特定技能外国人に対して日本語の習得支援をする必要がありますが、必ずしも日本語学校など専門機関に通わせることを指しているわけではありません。
日本で適切にコミュニケーションを取れるような日本語をマスターできる環境を提供するということです。
外国人が希望する場合は日本語学校に通わせるのもOKですが、その場合は受け入れ機関が費用を負担する必要もあります。
7.外国人からの相談・苦情への対応
仕事上や日常生活や社会生活に関する相談を受けた際は、外国人に適切な助言や指導を行う必要があります。
外国人を受け入れるには、困ったことが起こったときの相談や苦情を受けられるような体制を整えておくことが必要になってきます。
言語は、外国人が理解しやすい言語を使うことが原則です。
8.外国人と日本人との交流の促進に係る支援
定期的に日本人との交流の場を設けることが求められます。
スポーツイベントや食事会など、負担にならない頻度や時間帯が好ましいといえます。
9.非自発的離職時の転職支援
非自発的離職とは会社都合による離職などのことをいいます。
わかりやすくいえば、会社の事情など外国人自身が希望して離職したわけではない場合には、次の転職先を紹介するということです。
また、この支援にはハローワークの利用についての説明や同行なども含まれます。
10.定期的な面談・行政機関への通報
これは、受け入れ機関が労働基準法などに違反していないか確認することを指します。
支援責任者もしくは支援担当者が外国人を監督する立場の人と定期的に面談を行うもので、問題が発見されれば関係行政機関や労働基準監督署に通報されます。
任意項目を支援計画に追加するのも可能
上記10個の義務支援項目を加えて任意項目を支援計画に追加することも可能で、追加された場合、その任意項目の適切な実施も求められます。
よくある任意支援項目は下記の通りです。
- 入国時の日本の気候、服装についての情報をガイダンスに追加
- 雇用契約が解除された後にも、次の受け入れ先が決まるまで住居の確報
- 日本語能力試験(JLPT)の受験支援
- 日本語授業の受講料補助
- 資格取得者への優遇措置
- 交流イベントに参加する場合、有給休暇を取りやすくすること
支援計画の主な実施方法2つ
策定と出入国在留管理庁への提出だけでなく、支援計画の適切実施も1号特定技能外国人の受け入れ企業の義務となっております。
実施方法は主に2つあり、登録支援機関への委託か自社での内製化です。
登録支援機関に委託
登録支援機関とは、受け入れ企業の代わりに特定技能外国人の支援項目を実施する機関のことです。
支援項目の実施を登録支援機関に委託する場合、1号特定技能外国人支援計画書に当該機関の情報を記載しないといけません。
自社の工数削減というメリットがあるものの、1名の特定技能外国人雇用につき毎月3~5万円の支援費用がかかります。
5年間の雇用で考えると合計最大300万円の支援費用が発生するので、雇用数の多い場合、支援費用が膨大になってしまうかもしれません。
支援計画の内製化も可能
登録支援機関を利用しなくても1号特定技能外国人支援計画を自社で実施することも可能です。
この場合、先述の支援費用が発生しないため、ランニングコストを抑えるというメリットがあります。
一方、入管法や労働法の法律や関連する知識の習得のような初期工数がかかるというデメリットもあります。
今まで外国人雇用経験のない人事担当者の場合、初年度に月180時間の工数がかかるかもしれません。
初期工数がかかるとはいえ、社内にノーハウを蓄積できるとランニングコストがほぼ発生しないので、大人数かつ長期の雇用を考えていれば支援計画の内製化もぜひ視野に入れておきましょう。
まとめ
1号特定技能外国人を受け入れる場合、外国人の生活への支援が必要となります。
事前に1号特定技能外国人支援計画の計画書を作成して、国と外国人に提出します。
支援計画に含む必要がある項目は以下10個で、漏れのないように気を付けましょう。
- 入国前の生活ガイダンスの提供
- 入国時の空港への出迎え及び帰国時の空港への見送り
- 外国人の住宅の確保
- 在留中の生活オリエンテーションの実施
- 公的手続等への同行、各種行政手続についての情報提供と支援
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 非自発的離職時の転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
ウィルオブは採用から入社後の支援もすべて行っているため
初めて外国人材を採用する方も安心してお任せいただけます。