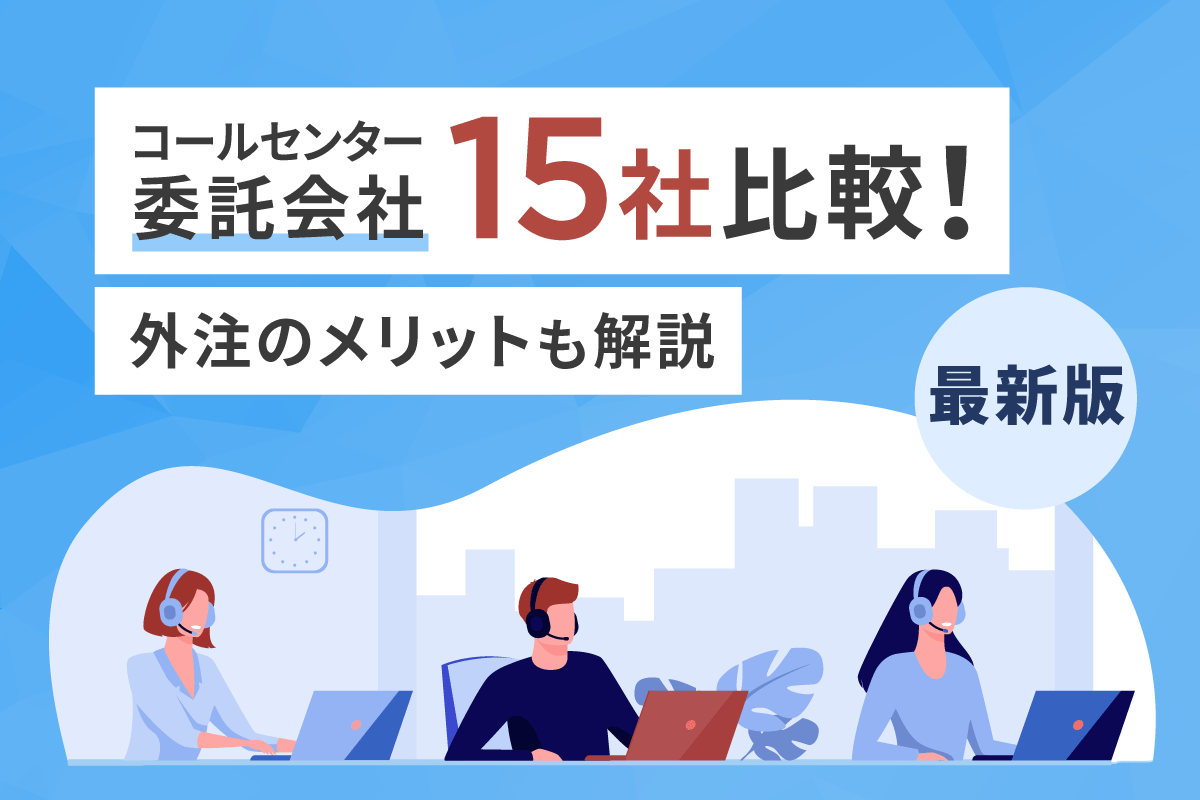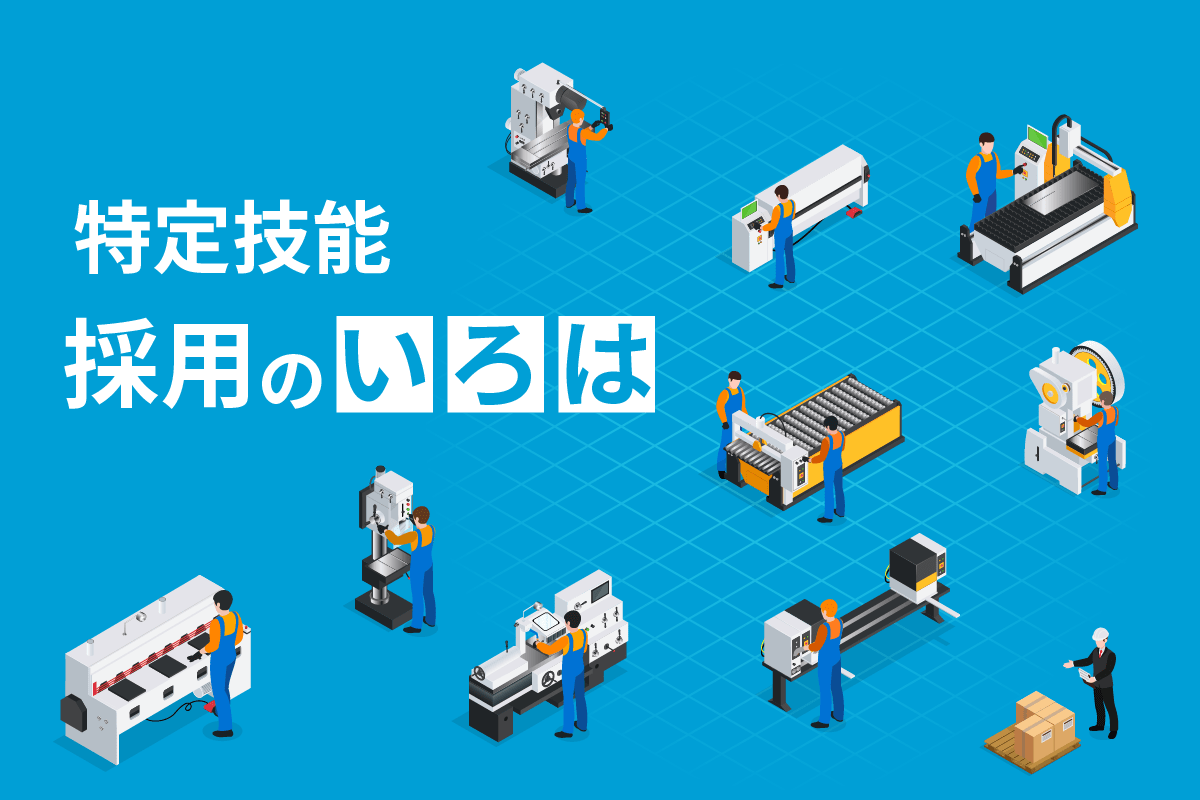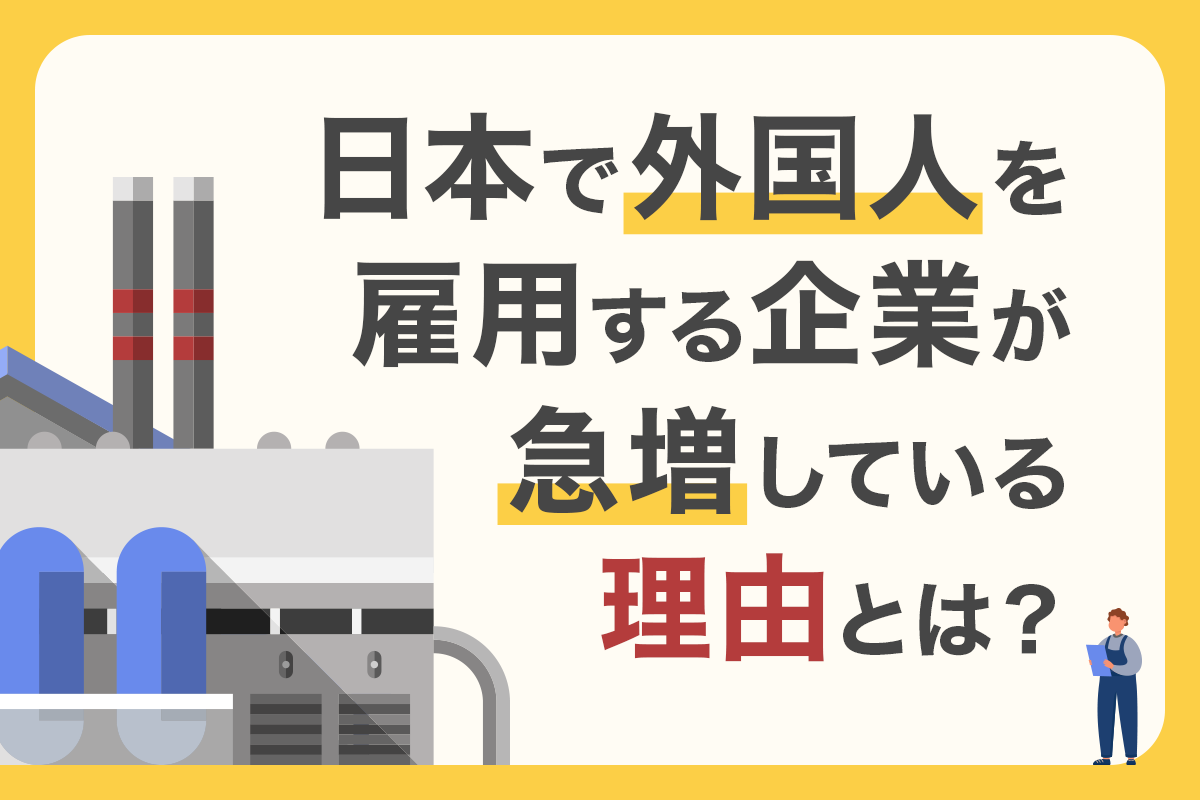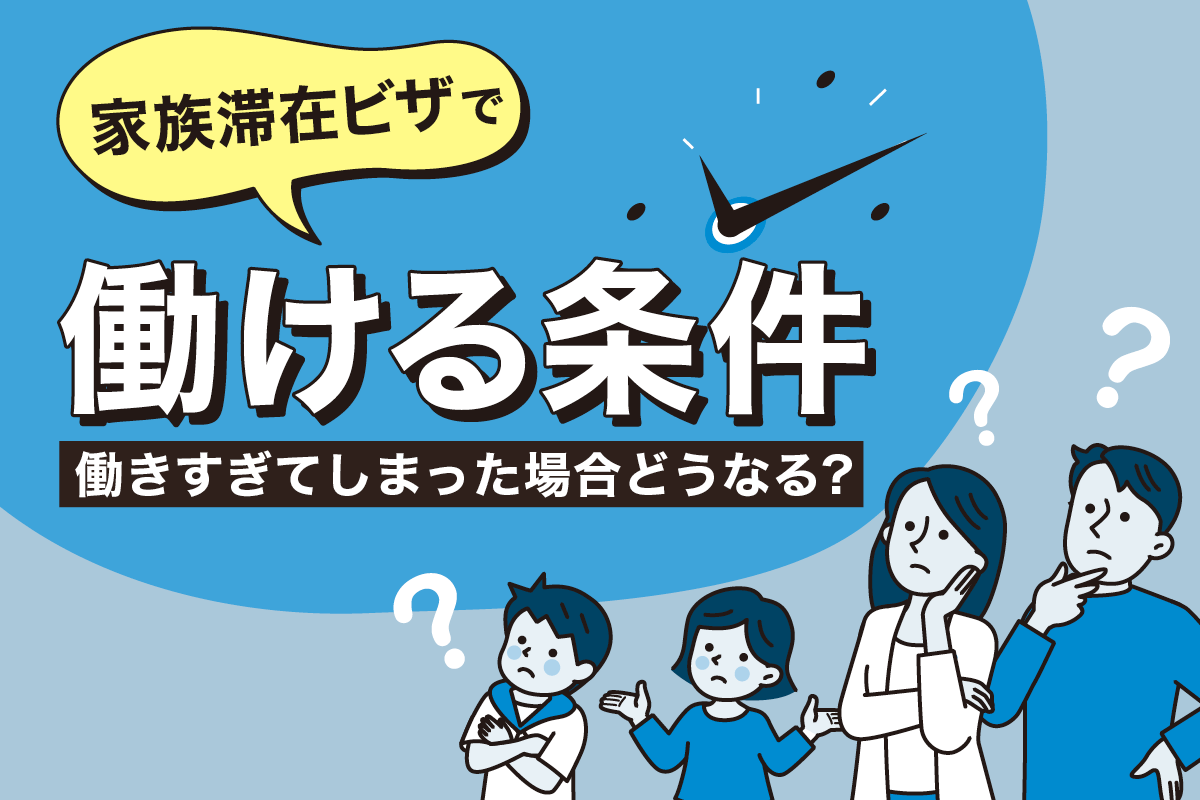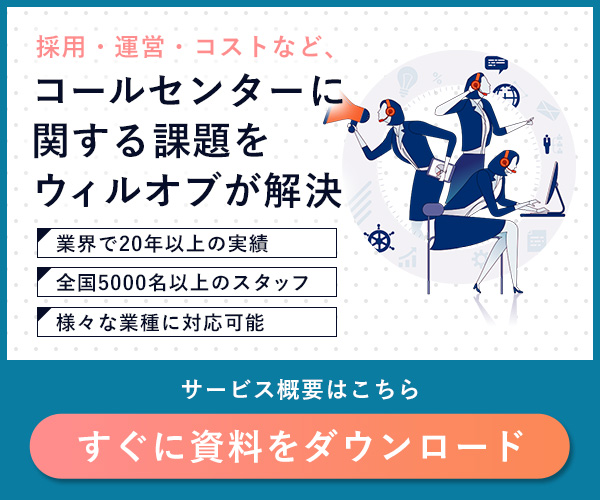【7月最新】コールセンター代行会社おすすめ7社!サービス内容や費用相場も比較
- アウトソーシング
- コールセンター
2025/07/01
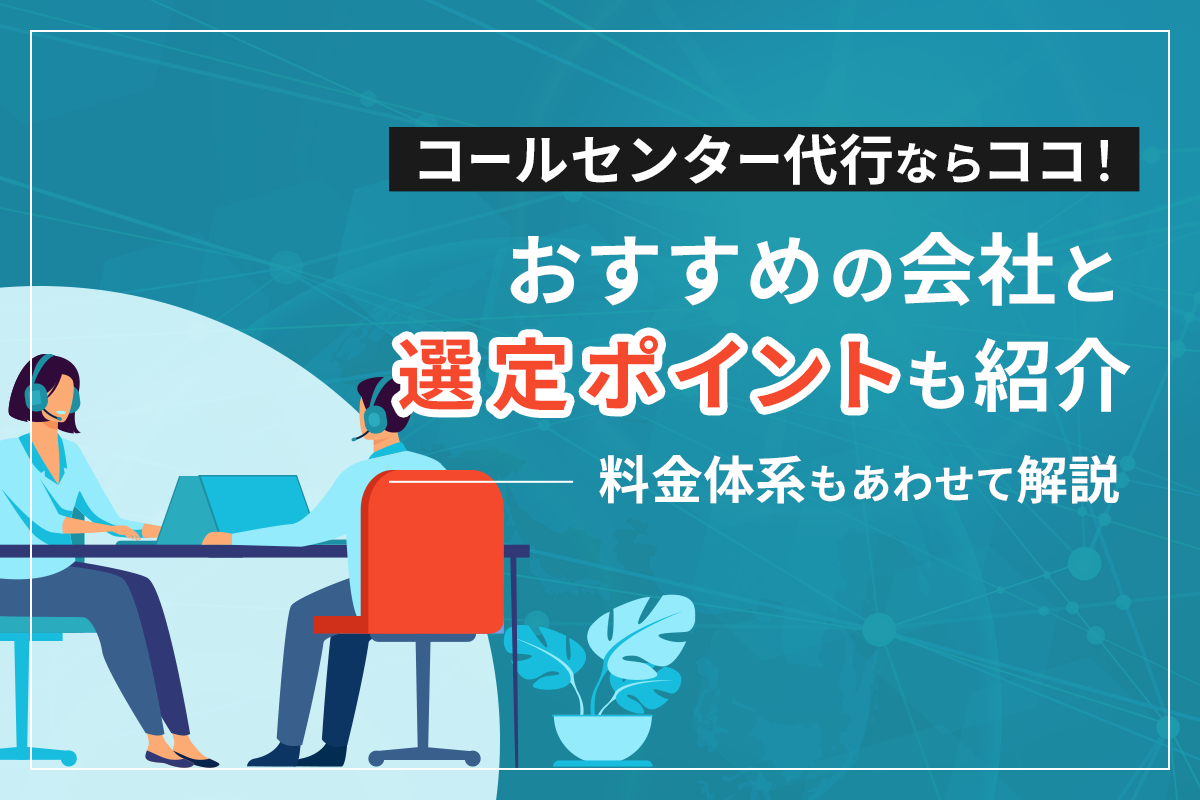
この記事でわかること
- コールセンター代行会社のおすすめ7社の特徴
- 自社運営と代行運営(外注)の違いと料金について
- 代行会社の活用のメリット・デメリットと選定ポイント
コールセンター代行サービスとは、企業と顧客をつなぐ重要な役割を果たすコールセンター(コンタクトセンター)の運営を、専門のサービス提供会社が代行する仕組みです。
一方、「本当に人件費を削減できるの?」「どの代行サービスを選べばいいのか、いまひとつ確証が持てない」と悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、コールセンター代行サービスのおすすめ7社を詳しく紹介します。各会社のサービスや選定ポイントまで解説します。
コールセンターの立ち上げにお困りではありませんか?
事業を円滑に進めるならウィルオブにおまかせください
TOPICS
コールセンター代行サービスとは
コールセンター代行サービスは、企業と顧客をつなぐ重要な役割を果たすコールセンター(コンタクトセンター)の運営を、専門のサービス提供会社が代行する仕組みです。
自社でコールセンターを構築・運営しようとすると、以下のような課題が発生します。
- 人件費:オペレーターや管理スタッフの採用・教育にかかるコスト
- 設備費:電話システムや専用ソフトウェアの導入・維持費用
- オフィス維持費:専用スペースの確保や賃貸料
- 管理負荷:日々の業務管理やトラブル対応、スタッフのシフト調整など
これらを解消し、手間やコストを最小限に抑えながら高品質なコールセンター運営を実現するため、「コールセンター代行サービス」の利用が広がっています。
コールセンターサービスの代行会社7社を紹介
ここではコールセンターサービスの代行会社7社をご紹介します。比較検討の材料として活用ください。
ウィルオブ・ワーク

【PR】
ウィルオブ・ワークは、東証プライム市場上場企業ウィルグループ(6089)のグループ会社で、コンプライアンス体制も整備されています。
20年以上のコールセンター代行実績と専門的な人材力が強みで、全国50以上の拠点ネットワークや自社運営のコールセンターを活用することで、人件費削減と高品質なカスタマーサポートを提供しています。
また、業務運営を現場のみで完結するのではなく、支援部門による外部フォローを強化しており、高い顧客満足度向上の実現に向け伴走する企業です。
| 法人問い合わせ | willof-work.co.jp |
| 提供サービス |
・カスタマーサポート |
| 料金体制 | 企業課題に合わせたカスタマイズプラン(相談可) |
| サービスの特徴 | ・様々な業界実績を誇るカスタマーサポート・ヘルプデスク ・低コスト・高品質でのセンター運営が可能 ・業界トップクラスの定着率96~97% |
コールセンターの立ち上げに関するご相談ならウィルオブにおまかせください。
e秘書

e秘書はベルシステム24が運営する30年以上の実績とノウハウを持つコールセンター代行サービスです。
24時間受付可能なほか、様々な言語に対応できるなど幅広いオプションが特徴です。サービスの利用時間など細かなプラン設定ができるため、クライアントの都合に合わせた利用も可能です。
| 提供サービス |
・電話代行 |
| 料金体制 |
月額固定費用 |
| サービスの特徴 | ・サービスプランが豊富&納得のコストパフォーマンス ・大規模コールセンター運営で培った30年以上の実績とノウハウ |
| 法人問い合わせ | tas.bell24.co.jp |
バディネット

バディネットはAKIBAホールディングスのグループ会社が運営するコールセンター代行サービスです。多様化する対応チャネルなど要望に対して最適なコールセンターソリューションを提供しています。
また高品質を提供するオペレーターのスキル定着と育成の為、段階的な研修を設計・実施しています。
| 提供サービス |
・カスタマーサポート |
| 料金体制 | 料金プランは企業に合わせて提案 |
| サービスの特徴 | ・24時間・365日の対応可能 ・インバウンド・アウトバウンドの多様な実績 |
| 法人問い合わせ |
フォンデスク

Fondeskは4000社以上の導入実績を誇る電話代行に特化したサービスです。法人、個人どちらでも利用できるサービスでIT業界サービスの事例が豊富なのが特徴です。
初期費用やオプションがないシンプルでわかりやすい料金プランも多くの企業から支持されています。
| 提供サービス |
・電話代行(一次受付に特化) |
| 料金体制 | 月額固定費用(月10,000円で利用可能)従量課金型(電話51件目以降200円)の混合 |
| サービスの特徴 | ・シンプルでわかりやすい料金プラン ・Chatwork、Slack、Microsoft Teams、LINE、Google Chat、Eメールなどの様々な通知方法を選べる |
| 法人問い合わせ |
NTTマーケティングアウトProCX

NTTマーケティングアウトProCX はNTTグループが運営するコンタクトセンターサービスです。コンサルティングやDX支援などコンタクトセンターを起点とした様々なプランを提供しています。全国各地200拠点以上のコンタクトセンターを構え、地域に根差した運営を目指しています。
| 提供サービス |
・コンタクトセンター |
| 料金体制 | 料金プランは企業に合わせて提案 |
| サービスの特徴 | ・全国各地200拠点以上の地域に根差した運営 ・多様なコミュニケーションツールに対応 |
| 法人問い合わせ |
スリーコール

スリーコールは、経験豊富なベテランスタッフがあらゆるお客様ニーズにあわせきめ細かく対応するよう教育に注力しています。また短期臨時からの受注から長期運用まで、幅広い期間の受託が可能で、全個室によるセキュリティ環境も魅力です。
| 提供サービス |
・セールスプロモーション業務 |
| 料金体制 | 企業課題に合わせたカスタマイズプラン(相談可) |
| サービスの特徴 | ・短期の臨時受注から長期運用まで幅広く対応 ・完全個室によるセキュリティ確保 |
| 法人問い合わせ |
SCSKサービスウェア

SCSKサービスウェアはコールセンターを中心にバックオフィスサポートやセールスマーケティングなど多岐にわたってサービスを提供しています。
グループの総合力を活かし、マルチチャネルに対応した次世代コールセンターをチャネル構築から評価分析までワンストップで運営できる強みがあります。
| 提供サービス |
・コールセンター |
| 料金体制 | 料金プランは企業に合わせて提案 |
| サービスの特徴 | ・「業務ナレッジ」×「IT」×「人財」で高品質サービス ・先端技術を活用したITソリューション |
| 法人問い合わせ |
失敗しないコールセンター代行サービスの選び方
コールセンターの代行サービスを活用し、顧客満足度の高いコールセンターを運営するためには、自社にあった代行会社を選ぶことが重要です。代行サービスを選定する際のポイントを解説します。
対応可能な業種や業務
代行サービス各会社は、得意な分野や不得意な分野が異なるため、代行会社の対応可能な業種・業務を確認しましょう。
インバウンド業務
インバウンド業務は主にお客様からの相談窓口やお問合せ窓口としての役割があります。主な業務は下記のとおりです。
| カスタマーサポート | 製品・サービスに関する顧客からの相談窓口 |
| ヘルプデスク | 商品やサービスの不具合や故障など、トラブルに関するお問い合わせ窓口 |
| テレフォンオペレーター(注文受付) | 顧客からの注文受付と発送手続き窓口 |
アウトバウンド業務
アウトバウンド業務は商談のアポイント設定や市場アンケート調査などがメインの業務です。主な業務内容は下記を参考にしてください。
| テレアポ(テレフォンアポインター) | 取引がまだない新規のお客さまに対して、商品・サービスの提案などを電話で行い、外勤営業の訪問や商談のアポイント獲得を行う |
| テレマ(テレフォンマーケティング) | 電話によるマーケット調査 電話によるアンケート回収などを行う |
取引実績
金融関係企業との取引実績のある企業はセキュリティに対するノウハウがあったり、大手企業との取引実績がある場合は大規模案件の対応ができるなど、取引実績は、その会社の扱うことのできる業界を示す重要な手がかりとなります。事前の調査やヒアリングがおすすめです。
スタッフの定着率
スタッフの定着率にも着目すると良いでしょう。
スタッフの定着率が低いセンターは対応品質が上がらない可能性があります。逆にスタッフの定着率が高いセンターはベテランと呼ばれる高スキルのコールセンタースタッフが在籍しているため、品質の向上が早期に見込めます。
業務改善対応の可否
業務のアウトソースだけでなく、業務の改善や効率化を目指す場合は、業務フローの最適化や実施体制の構築を提案できるサービスを選ぶのがおすすめです。
自社が抱える課題解決に貢献できるかを確認し、自社商品やサービスを深く理解し、即戦力となる代行会社を選ぶことが大切です。
料金体制
料金体系は代行会社やサービス内容によって大きく異なりますので確認しておく必要があります。
コールセンターを外注する際に、優先すべきことは顧客満足度向上と費用対効果の最大化です。コスト削減を追求するあまり、品質の低い代行会社を選択してしまうリスクがあります。
料金体系は主に「従量課金型」「月額固定型」「成果報酬型」の3つに分類されます。
インバウンド業務におすすめ:「従量課金型」「月額固定型」
インバウンド業務におすすめの料金体系は従量課金型もしくは月額固定型です。
コール件数に応じて課金される「従量課金型」はコール件数が少ない場合におすすめです。一方、コール件数が多い場合は1件当たりのコール単価が安い「月額固定型」を検討しましょう。
アウトバンド業務におすすめ:「成果報酬型」
アウトバウンド型業務に多いのが「成果報酬型」です。
アポ獲得や新規会員獲得といった成果に応じて料金が発生するのが特徴で、無駄なコストを抑制したい場合におすすめです。
なお、インバウンド・アウトバウンドともに基本料金や初期費用が設定されている場合があるため、事前に確認しておきましょう。
サービスの品質
業務内容、料金だけでなく、顧客対応のサービス品質を確認することも重要です。
- スタッフの人数
- 人員体制
- 対応可能な日時
- 分析やレポーティング
- 実績
- セキュリティの安全性
- スタッフの定着率
上記だけでなく、代行会社を選ぶ際は、質の高いカスタマーサポートサービスを提供するため採用力や人材育成に注力しているかも基準とすることをおすすめします。
コールセンターの立ち上げに関するご相談ならウィルオブにおまかせください。
代行運営と自社運営の費用を比較
コールセンターの運営において、自社で運営する場合と代行会社を利用する場合の費用についても解説します。
自社運営の場合
自社でコールセンターを設けて運用した場合にかかる一般的な費用は大きく分けると「初期導入費用(イニシャルコスト)」「維持費用(ランニングコスト)」「ライセンス料」の3つです。
| 詳細 | 相場 | |
| 初期導入費用 (イニシャルコスト) |
システム導入費(CTIなど)、機材費や通信費、ネットや電話回線の工事費用(設置費用) |
約30~250万円 |
| 維持費用 (ランニングコスト) |
月額固定費用 ※規定もコール件数を超過すると超過料金がかかる(コールオーバー料金) |
約3~70万円 |
| ライセンス料 | 外部システムとの契約料 (ライセンス料) |
年間約50万円 |
上記費用を踏まえた費用合計は83~370万円ほどのコストがかかります。
人件費はコールセンターの人員数によって変動が大きいため相場の費用よりも高くなることがあります。
代行サービス会社の場合
代行会社を利用した場合、システム導入費や機材・通信費はかからないため自社で立ち上げるよりも安い導入が可能です。代行会社や業務内容によって料金体制は異なりますが、主に「従量課金プラン」「定額料金プラン」「成果報酬プラン」の3つがあります。
| 業務内容 | 詳細 | 相場 | |
| 従量課金型 | インバウンド | 対応したコール数に応じ費用が発生 | 数百円~1,000円 ※1コールあたり |
| 定額料金型 | インバウンド | 設定したコール件数までは月額固定費用 ※設定したコール件数を超過すると超過料金がかかる (コールオーバー料金) |
月10~30万円 ※月間コール数が数十件~数百件の場合 |
| 成果報酬型 | アウトバウンド | ・アポ単価×アポ獲得数 ・受注単価×受注数 など |
1件10,000円~ ※業種や商材に よって変動 |
従量課金型はコール件数の少ない場合は費用を抑えて利用することができます。コール件数の多い場合は月額固定型を利用したほうが1件当たりのコール単価は安くなるため、おすすめです。ただし、設定したコール件数を超えてしまうと超過料金(コールオーバー料金)がかかってしまうため注意しましょう。
成果報酬型は主にアウトバウンド業務で導入されており、アポイント獲得や受注数など決められた目標を達成した際に費用が発生します。そのため、無駄な費用を抑えることができるといったメリットがあります。
コールセンター代行サービスのメリット
ここまでコールセンター代行についてや運営にかかる費用をご説明しました。次に具体的な代行サービスを利用するメリットを紹介します。
コストを抑えた最適な運営が可能
自社のコールセンターを一度構築すると、ランニングコストが低いと誤解されがちです。しかし、実際には人件費やオフィス維持費、設備費など、膨大なコストがかかるだけでなく、マネジメント業務などのリソースも必要です。
また、採用や育成などの人件費やシステム整備料などの固定費は継続的に発生するため、トータルストが高くつくケースが一般的です。
代行サービスは自社のリソースを最小限におさえながら、運営にかかるトータルコストを効果的に管理できる点がメリットとになります。
高品質なコールセンターの運営
コールセンター代行会社は専門性からサービス品質が高い会社が多くあります。コールセンターの「品質」は、一般的に「応対品質」「運用品質」「接続品質」「処理品質」の4つと言われています。
| 応対品質 | お客様の問い合わせに対して丁寧かつ迅速な対応ができているか |
| 運用品質 | コールセンターの目標(KPI)達成のための最適な運営・運用 |
| 接続品質 | 問い合わせのつながりやすさ |
| 処理品質 | 問い合わせに対する適切な対応・処理ができているか |
お客様が問い合わせをし、最初につながるコールセンターは企業の顔とも言えます。お客様は問い合わせに対する担当者の対応でその企業の印象を決めると言っても過言ではありません。加えて、お客様の生の声をヒアリングでき、その情報をもとに企業のブランディングや今後の事業に活かす戦略を立てることができます。
代行会社では専門的な知識を持つ「電話対応のプロ」がクレーム処理やトラブル処理などの難しい業務の場合でも高い品質で対応するため、顧客満足度の高いコールセンターを目指すには代行会社を利用することをおすすめします。
運営ノウハウがない場合でも短期間で運営が可能
自社でコールセンターを運営しながら品質を確保することは、時間と労力がかかるため、コールセンター立ち上げができない企業は少なくありません。
しかし、代行サービスを活用すれば専門的な知識やスタッフが提供され、短期間でのコールセンター導入が可能になります。ノウハウが全くない企業でも代行サービス導入することは非常にメリットがあると言えるでしょう。
コールセンターの立ち上げに関するご相談ならウィルオブにおまかせください。
コールセンター代行サービスのデメリット
社内のノウハウ蓄積が困難
代行会社にコールセンター業務を委託する形になるため、自社社員へノウハウや経験が蓄積されにくいということがあります。将来的に内製を検討されているようであれば代行会社のノウハウを貯蓄しやすいサービスの手順書やマニュアルを作成、または共有してもらえる会社を選びましょう。
セキュリティの安全性
代行会社を利用することによって自社の情報を共有することになるため、情報漏えいのリスクが高まります。安全性の高いセキュリティシステムを利用している代行会社を利用するなど、セキュリティ対策をしっかりと行っている会社を選ぶようにすることも必要です。
まとめ
この記事では、コールセンター代行について、代行会社の選定ポイントや料金体制や、メリットとデメリットなどのご紹介しました。
自社のコールセンターを構築・運営するには、人件費やオフィス維持費、設備費などの膨大なコストがかかるだけでなく、品質の維持や向上などのマネジメント業務もリソースも必要です。
リソースを最小限に押さえながら、高い品質でコストが抑えることが可能な「コールセンター代行サービス」の導入を検討してみましょう。
コールセンターの立ち上げにお困りではありませんか?
事業を円滑に進めるならウィルオブにおまかせください
よくある質問
コールセンターを代行する際のメリットを教えてください。
はい。低コストでの運営・短期間での運営開始・高品質なコールセンターの運営などがメリットとしてあげられます。詳細は「コールセンター代行のメリット」で説明しているので確認ください。
代行会社を選定する際にポイントを教えてください。
はい。対応業種や業務・料金体制・サービスの品質などが選定ポイントとしてあげられます。詳細は「コールセンター代行会社の選定ポイント」で説明しているので確認ください。