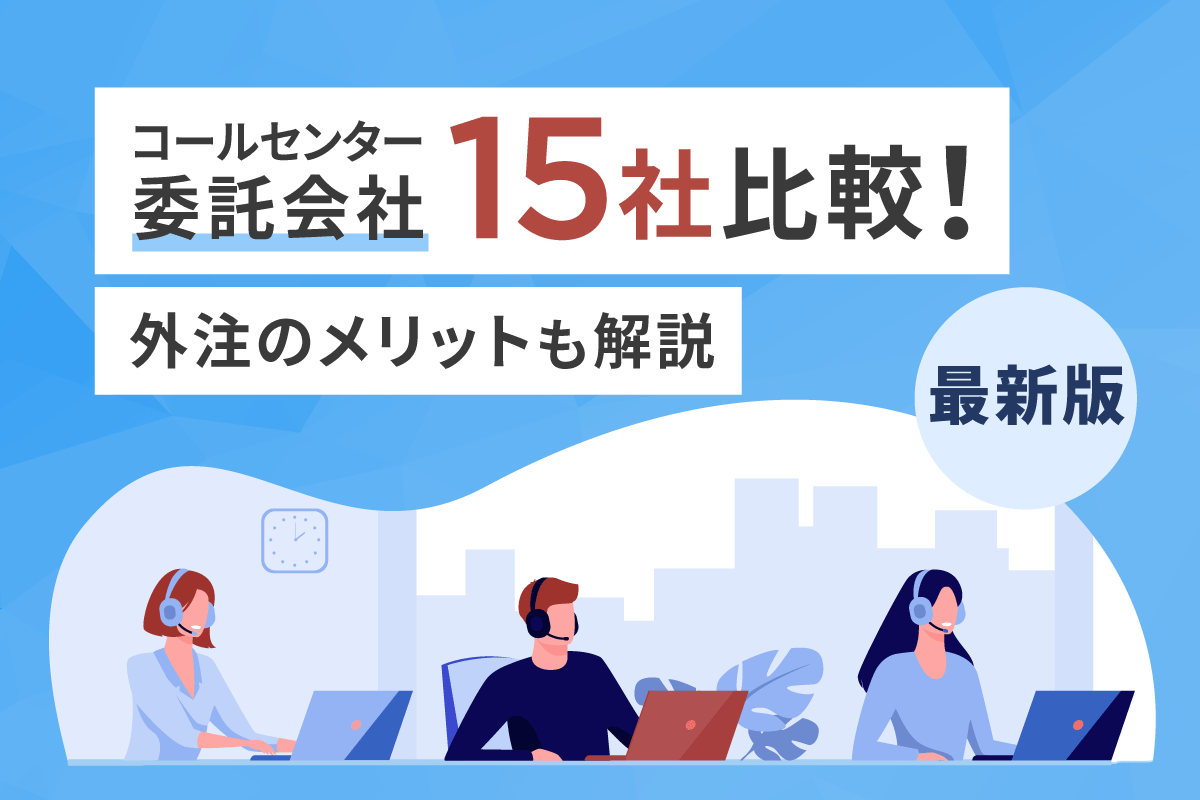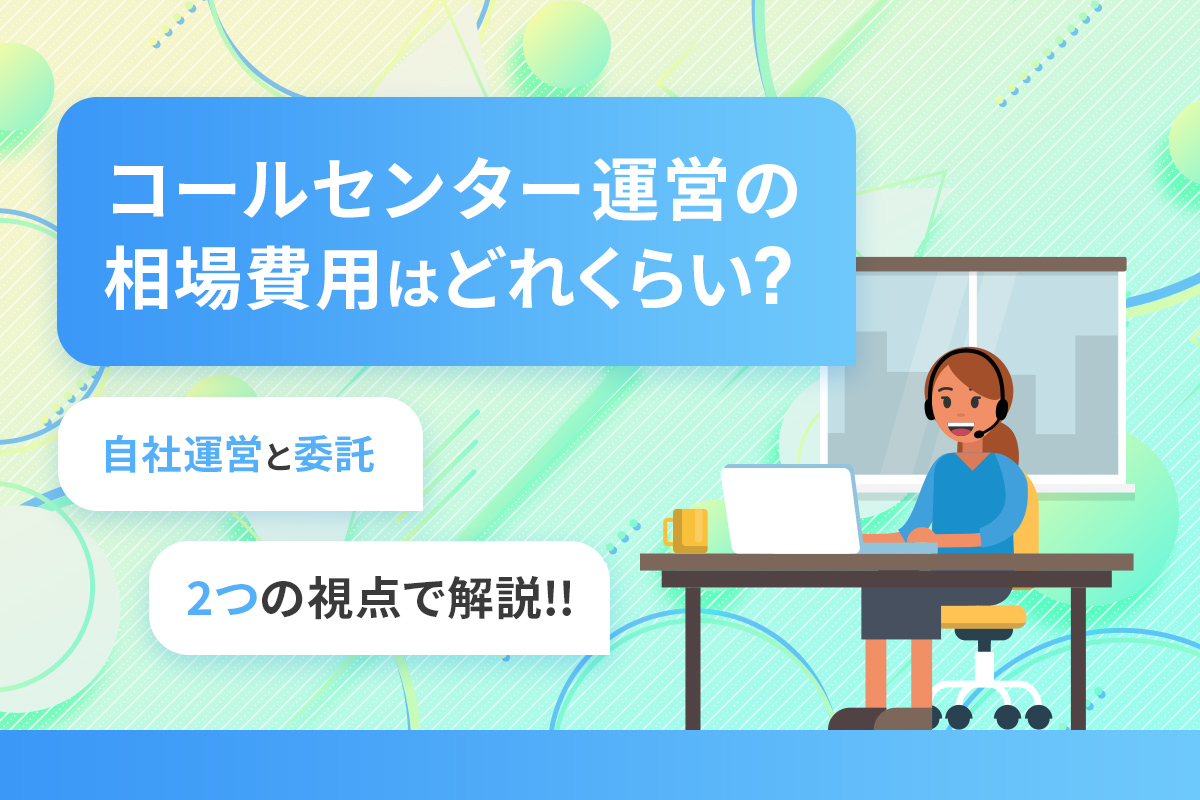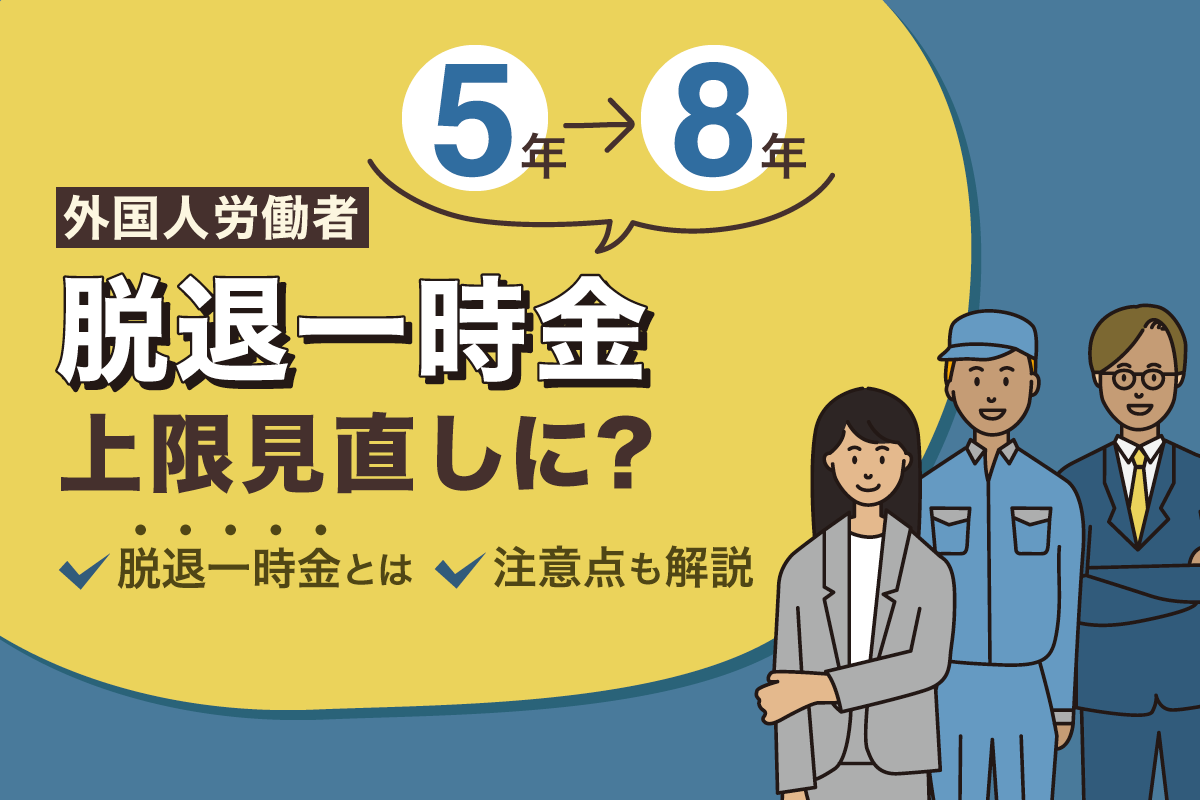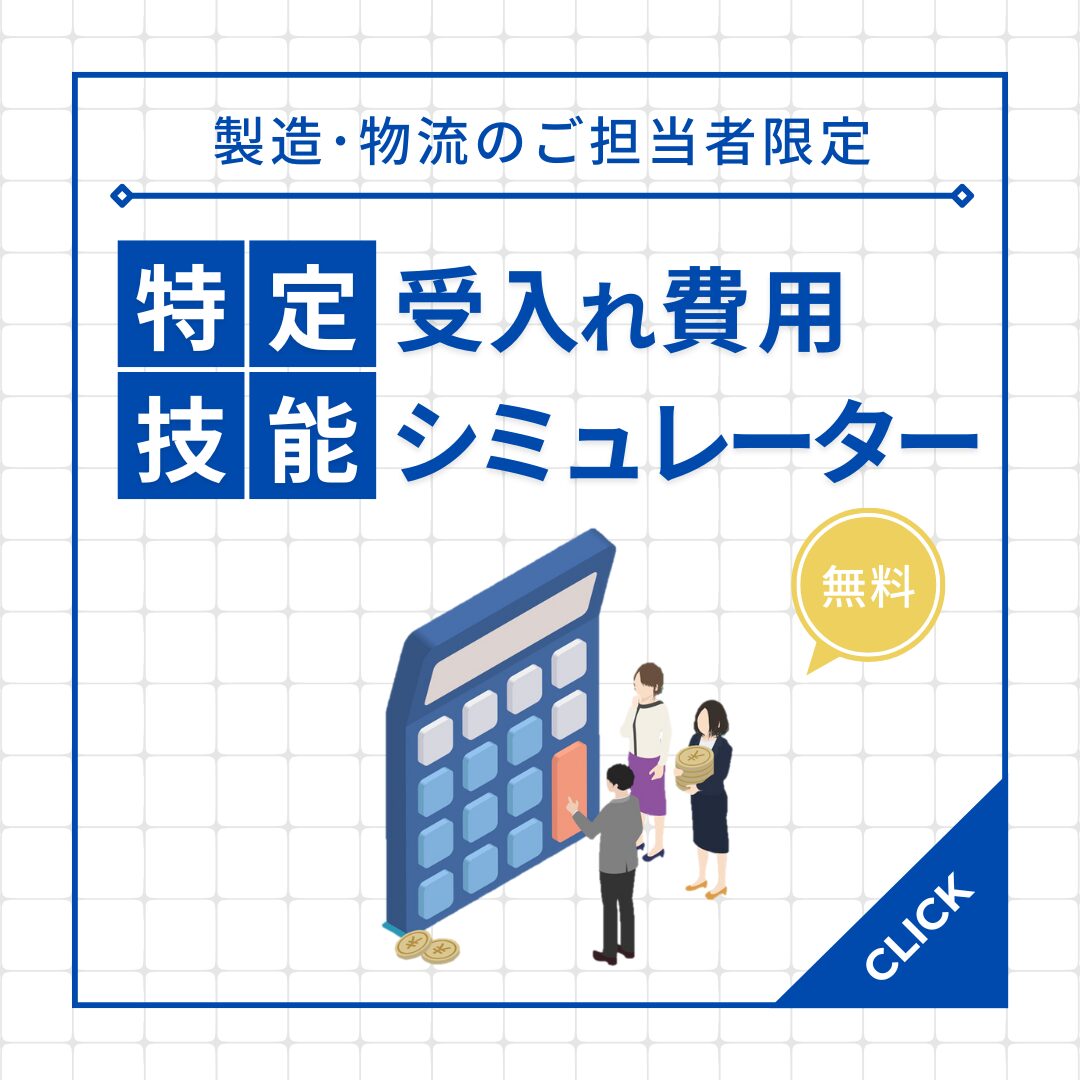日本で外国人を雇用する企業が急増している理由とは?
- 外国人採用タイムズ
- 投稿
2025/08/27
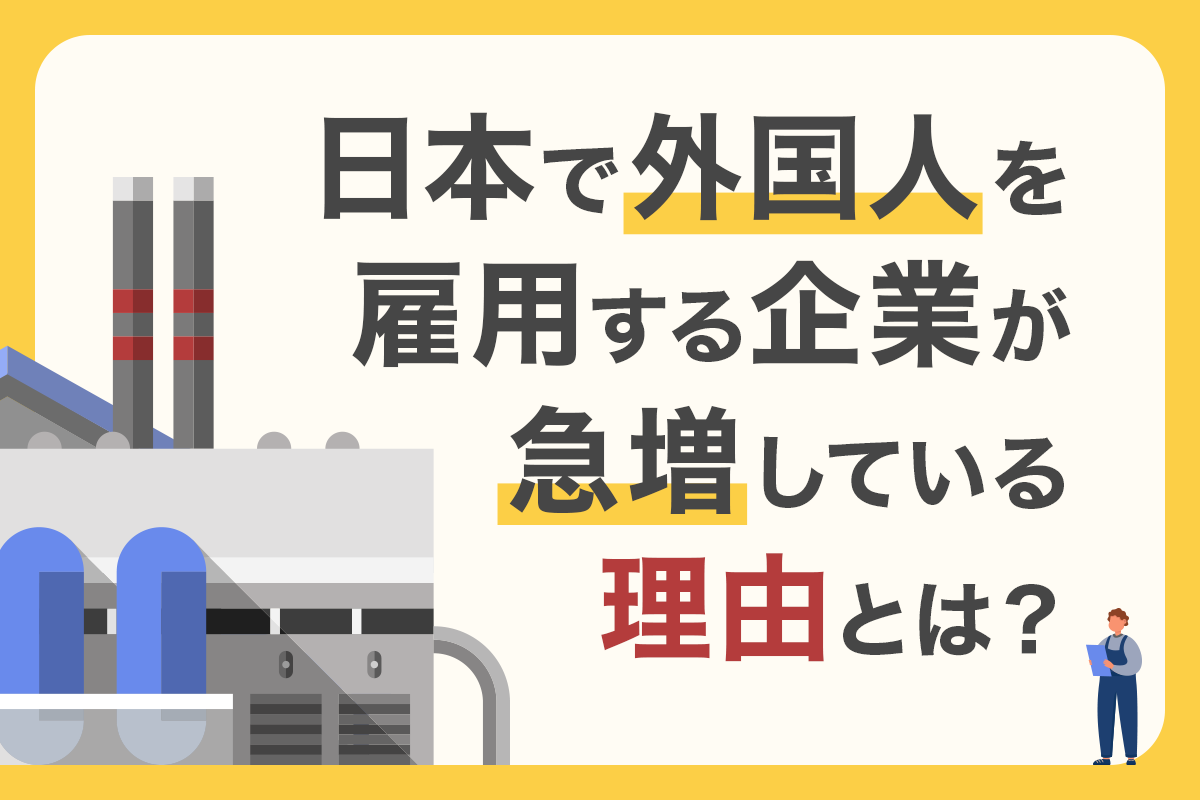
この記事でわかること
- 外国人を雇用する企業が急増する理由
- 外国人を雇用する手続き
- 外国人を雇用する際の注意点
大手企業の製造工場をはじめとする多くの企業で、外国人の雇用比率が急激に増えています。
それはなぜか? 彼らの勤勉さや上昇志向などがポイントに挙げられますが、それだけではありません。 高齢化社会に突入する日本の特徴に理由があるのです。
▼日本で雇用できる外国人の特長(ビザの比較など)を分かりやすくまとめた資料です。
よろしければ、外国人雇用にお役立てください。

▼こちらの記事では安心して利用できる人材会社をまとめています。ぜひご活用ください。
【最新】外国人人材に特化 採用・紹介サービスおすすめ13選|メリット・注意点も解説
TOPICS
外国人を雇用する企業が急増する理由とは
2010年、日本の人口は約1億2800万人でした。しかし、 2030年には1億1600万人に減少すると言われています。
人口の減少に対して、日本の高齢化は歯止めがきかない状況に陥っているのです。 (じつに人口の1/3近くが65歳以上になると予想されています)。そのため、 労働人口が今より減少するのは間違いがなく、将来が不安視されています。
そこで注目されているのが外国人労働者です。日本で働く外国人労働者は、2016年には100万人を突破し、2019年には160万人を超えました。
2020年は、新型コロナ感染症の拡大による外国からの入国規制で、新たな外国人雇用は停滞しました。年内に一旦は緩和の兆しが見えましたが、2021年に入ってから再び感染が拡大しています。しばらくは感染者の増加と減少の繰り返しが続きそうです。外国人雇用を計画する企業は、今後の規制や規制緩和の情報を確認しながら進めていく必要があります。
ただ、日本が抱える人手不足の状況は変わりません。長い目で見れば、外国人労働者の数は今後も増え続けるでしょう。
日本政府も、外国人の雇用管理に力を注ぎ、雇用確保に尽力している最中です。外国人労働者にとっても良い環境が整ってきているからこそ、 職を求めて来日する外国人が増えていると言っても過言ではありません。
日本は労働者が減少し、反比例するように在留外国人が増え続けている……。 将来を見据えて成長しなければならない企業が、彼らに目をつけないわけがありません。 働き手が欲しい企業と、働きたい外国人。 ウインウインの関係が成立しているからこそ、外国人雇用の増加に繋がっているのです。
【参考】
■組織行動研究所『国内人口推移が、2030年の「働く」にどのような影響を及ぼすか | 2030年の「働く」を考える』
■三井住友アセットマネジメント株式会社『投資信託・投資顧問の三井住友DSアセットマネジメント日本経済】増え始めた外国人労働者PDFより』
外国人を採用するメリットとデメリットについて
大手企業が先陣を切って進めていた外国人採用ですが、現在では中小企業も外国人採用の可能性に注目するようになっています。
ただ、外国人を雇用することで発生するデメリットがあるのも事実です。外国人を雇用するための準備や運用が複雑で、雇用主となる企業に大きな負担がかかります。
ひとくちに外国人を雇用するといっても、日本人とは労働条件が異なるので注意しなければなりません。
例えば、雇用主が外国人のAさんを採用したとします。Aさんから口頭で“日本で働くための在留資格”を持っていると報告されたため、雇用主側は在留カードを確認しませんでした。
しかし、3ヶ月後、Aさんが“日本で働くための在留資格”を持っていなかったことが発覚。 Aさんはもちろん、雇用主も罰則の対象になった……。このようなケースが少なからずあるのです。
では、外国人を採用するための知識を持たない企業は、 リスクを回避するため雇用を諦めた方が良いのでしょうか? そんなことはありません。下記で紹介しましょう。
外国人採用のメリットは、少子高齢化をはじめとした諸問題による人材不足を解消できることです。スキルがない人材では、実質の問題解消には繋がりません。その点、外国人には成果を出すことに積極的で、バイタリティー溢れる人物が多いため、人材不足の解消に繋がりやすいでしょう。
また、外国人ならではの発想で課題解決や業務の質改善なども期待できます。そのほか、外国の文化を知っていることで、海外進出の際の強力な戦力になるでしょう。外国人採用にはデメリットもありますが、このようにメリットの方が大きいことが特徴です。
労働者(外国人人材)側のメリットとデメリットについて
労働者側のメリットは、健康保険や雇用保険などの制度が充実していることです。年1回の健康診断によって結果的に医療費を削減できたり、会社によっては交通費が支給されたりと、さまざまなメリットがあります。
そのほか、世界トップレベルとされる日本の顧客対応を学べることもメリットです。次のステップへ進むための足がかりになるでしょう。そのほか、日本では不当解雇が行われることが稀なため、安定的に働けることもメリットです。
労働者側のデメリットは、年功序列でスキルが給与に反映されない会社があることです。このリスクを避けるために、外国人人材は働く企業を選定/判断する段階でチェックするでしょう。
日本では採用側(企業)の立場のほうが強い傾向にあり、給与などの条件交渉はタブー視されているかもしれません。しかし、スキルに対して給与が低いと感じた外国人人材は、採用面接の段階で交渉してくることもあるでしょう。
外国人を雇用する手続き
海外にいる外国人を招聘したい場合
技能実習生や特定技能の場合、高校卒業者でも問題ありませんが、技術・人文・国際業務という高度人材のビザで海外から人材を採用したい場合は、専門学校または大学を卒業している必要があります。その学校は国内外を問いません。基本的には、面接で内定が決まった後に雇用契約書を締結しなければなりません。この雇用契約書をもとに、外国人労働者は現地の日本大使館で在留資格認定証明書(COE: Certificate of Eligibility)の申請を行います。日本の空港に入国する際にCOEを提出することで在留カードが発行され、入国後すぐに契約を交わした会社で勤務を開始することができます。技能実習生や特定技能の場合、これらの手続きは現地の送り出し機関が手配しますので、特に心配する必要はありません。
日本国内の専門学校や大学で在席中の留学生を新卒採用したい場合
専門学校や大学に在籍している学生の在留資格は「留学生」です。学校卒業後に新卒として採用したい場合は、雇用契約書、出席証明書、成績証明書を出入国在留管理局に提出し、「技術・人文・国際業務」というビザに切り替える必要があります。ただし、すべての申請が必ず許可されるわけではありません。審査においては、学校で学んだ知識が入社後の業務にどのように活かせるかが判断されます。審査がスムーズに進むように、採用理由書の提出もおすすめです。
日本で就労中の外国人を中途採用したい場合
既に「技術・人文・国際業務」のビザを取得し、日本で働いている外国人を中途採用したい場合、4.2のように、留学生から「技術・人文・国際業務」への在留資格変更許可申請をしなくても問題ありません。ただし、新しい転職先での業務内容が過去に申請した内容と変わらないか、または学校で学んだ知識がどのように活かせるのかを出入国在留管理局に確認することをお勧めします。業務内容が変わらない場合は確認は不要ですが、確認をせずに新しい職場での業務を続け、その後に業務内容が不適切だと指摘されると、強制帰国となる可能性があります。そのため、外国人の転職者を受け入れる際には、「就労資格証明書」の取得をお勧めします。
外国人をアルバイトとして雇用したい場合
アルバイトとして採用できる在留資格は、永住者と定住者を除けば、留学生と家族滞在のビザのみです。特に留学生の場合、アルバイトは週28時間以下というルールが設けられています。Wワークを行う場合は、2ヶ所の勤務時間の合計が週28時間以下である必要があります。また、夏休みや冬休みなどの長期休暇中は、週40時間まで働くことができます。アルバイトを採用する際には、在留カードの裏面に「資格外活動許可」が記載されているかどうかを必ず確認してください。
外国人を雇用する際の注意点
在留資格の取得
上記の4.1と4.2の場合に該当する内容です。外国人に交付される在留カードには、1年、3年、5年の3つの期限があります。在留期間は受け入れ企業の規模や外国人の学校での実績、経験によって異なります。期限がありますので、期限満了の3ヶ月前には近くの出入国在留管理局で在留資格の更新手続きを行う必要があります。手続きを忘れた場合、どんな理由であっても不法滞在と見なされ、強制帰国となることがあります。このため、外国人を採用する際には、入社後の在留期限の管理にも注意が必要です。在留資格更新の手数料は、窓口で6,000円、オンライン申請の場合は5,500円となります。
就労資格証明書の取得
上記の4.3に該当する内容です。就労資格証明書の申請は、在留資格変更とほぼ同じ手続きです。雇用契約書のほかに、学校の成績証明書などが必要となります。取得には手数料はかかりません。許可が下り次第、現在所持している在留カードをもとに新しい会社での勤務を開始できます。
資格外活動許可の申請
上記の4.4に該当する内容です。資格外活動の申請は無料で、申請当日に即座に結果が出ます。資格外活動の許可を得ていない留学生を採用した場合、企業は不法就労助長罪に該当し、懲役刑や数百万の罰金といった処罰の対象となりますので、十分に注意してください。
外国人を採用する企業の今後の課題3つ
外国人を採用するときの課題は、次の3つです。
コミュニケーションの問題
基本的な日本語ができていても、微妙なニュアンスの違いによる認識の不一致はよく起こります。また、日本人は細かなところまで確認せず、予想で行動するケースが少なくありません。意味をわかっているだろうと自己判断して業務を進めると、大きなトラブルに発展してしまうこともあります。
難しい日本語は、意味を理解しているか逐一確認することが大切です。各種マニュアルを母国語で作成したり、動画や画像など視覚的なツールを準備したりしておくと理解促進に役立ちます。
外国人人材に理解や日本語スキルを求めるばかりでは、良好なコミュニケーションは難しいものです。日本人社員に対する、指示の出し方やきちんと伝わったかを確認するなどのルール作りも求められます。企業や社内人材側も、外国人人材の状況やスキルレベルの理解に努めることが大事です。
また、社員の英語スキルを向上させる施策も、社内コミュニケーションの問題を解決する大きな一助となるでしょう。
文化と風習の違いによる問題
国が違えば、文化や風習、宗教まで違います。文化や風習、宗教を理解したうえで、適切な対応をとりましょう。例えば、社員食堂がある場合は、宗教上の理由で特定のものを食べられないことに配慮して、別メニューを用意する必要があるでしょう。また、毎日礼拝する慣習を持つ宗教もあります。礼拝に活用できる場所を社内に設置している企業もあります。
外国人人材を雇用する場合は、受け入れ前の段階から文化や風習、宗教など、人材のバックグラウンドの理解に努めましょう。担当者だけでなく、ともに働く全社員が理解・協力できる体制づくりが必要です。
雇用のための手続きが複雑
外国人採用と日本人の採用では、必要な手続きが異なります。それぞれの手続き方法をしっかり分けて適切に行わなければなりません。
最初は、必要書類の入手方法や採用後の手続きなどで手間取る可能性があります。それ以上に外国人採用のメリットは大きいですから、課題解決に向けて積極的に取り組んでいきましょう。根気強く、正確に、かつ必要な手続きやその準備は、早め早めの着手がおすすめです。
信頼のおける人材会社のサポートを受けながら進めていけば、法に則ったスムーズな外国人採用が実現できます。煩雑な手間も一気に省くことができるでしょう。
ただし、人材会社のサポートを受けるとしても、事前に外国人採用・雇用の知識はつけておきたいものです。知識があると自社に合った人材会社を選ぶのもスムーズになるはずです。こちらの記事に採用・雇用に必要な知識や関連する内容をまとめています。ぜひ参考にしてください。
▼関連記事
【失敗しない外国人の採用・雇用】必要な基礎知識や外国人人材紹介会社の選び方をまとめて解説
外国人の雇用はプロに任せるのが一番の近道
「外国人の採用実績がない」「届出や手続きをどうすれば良いのか分からない」といった、 さまざまな理由で外国人の採用に、二の足を踏む雇用主は少なくはないでしょう。
そこで活用してほしいのが、外国人の採用から就業するまでの手続きを一括で アウトソーシングできる人材サービスです。
外国人の人材サービスを専門とする企業であれば、優秀な外国人を抱えています。将来的に外国人人材を増やしていく計画があるなら、 日本語と母国語を話せる優秀なバイリンガル人材など、優秀な人材は必要不可欠な存在となっていくでしょう。 時には雇用主と現場をつなぐ通訳として、時には外国人労働者の指導を担う リーダーとして、大活躍することが予想されます。
こうしたサービスを利用することで、面倒な手続きを踏まずに、 短期間の内にニーズに合った人材に出会うことが叶います。外国人に特化した人材会社はそれぞれ特徴や強みも異なりますので、自社に合った人材会社を選ぶようにしましょう。
こちらの記事では安心して利用できる人材会社をまとめています。ぜひご活用ください。
▼関連記事
【最新】外国人人材に特化 採用・紹介サービスおすすめ13選|メリット・注意点なども解説
まとめ:信頼できる人材会社にアウトソーシングしよう
外国人の採用・雇用は、アウトソーシングするのがお勧めです。 とはいえ、依頼する人材会社をしっかり選定することも大切なミッションとなるでしょう。
すべてを任せて安心していたが、人材会社が行った在留資格の確認が不十分で 不法就労の罰則の対象になってしまった。しかもアウトソーシングしていた人材会社は雲隠れ……。
こんなことが起こらないように、信頼できる人材会社に頼むことが重要です。 実績は豊富か、サービス内容は充実しているのかなどを確認するためにも、 まずは相談するところから初めてみてはいかがでしょうか。
外国人登録者数およそ3万人。特定技能に関しても飲食料品製造分野で、すぐに就業が可能な人材が随時100名以上(切り替え希望で登録)おります。ご希望の雇用スタイルや在留資格になどお気軽にご相談ください。