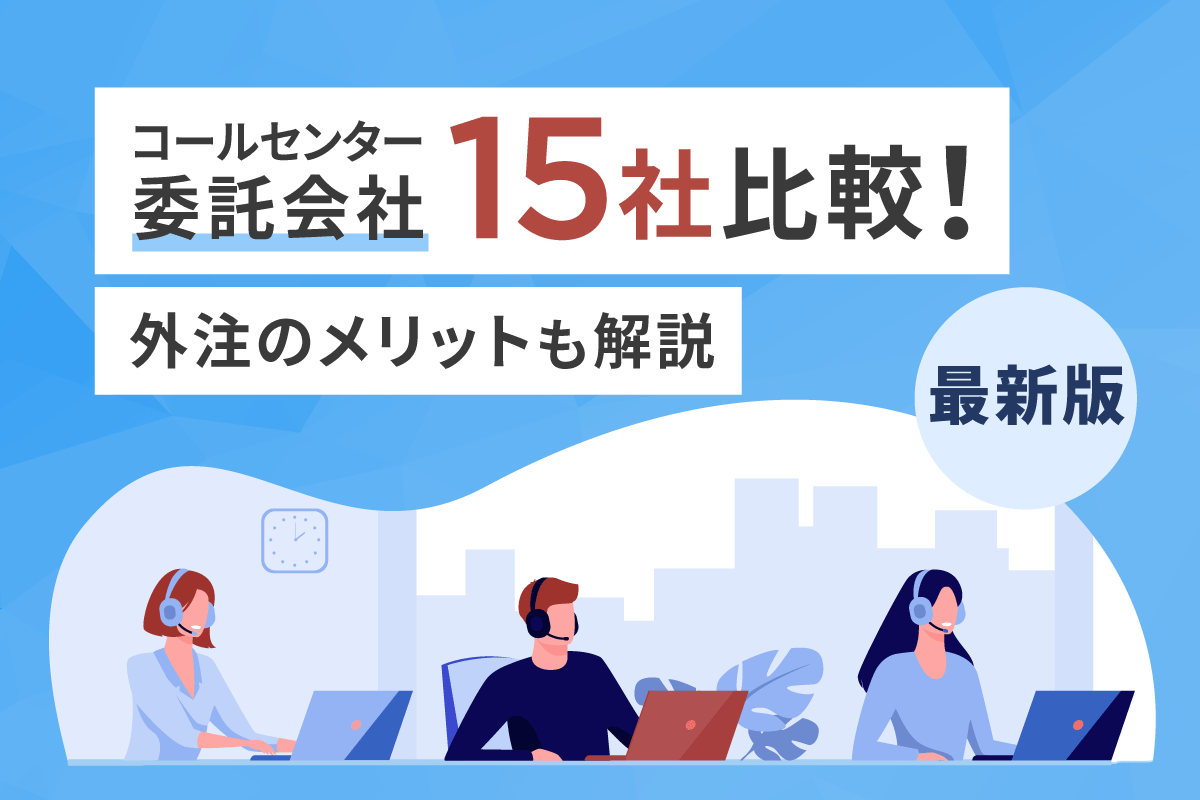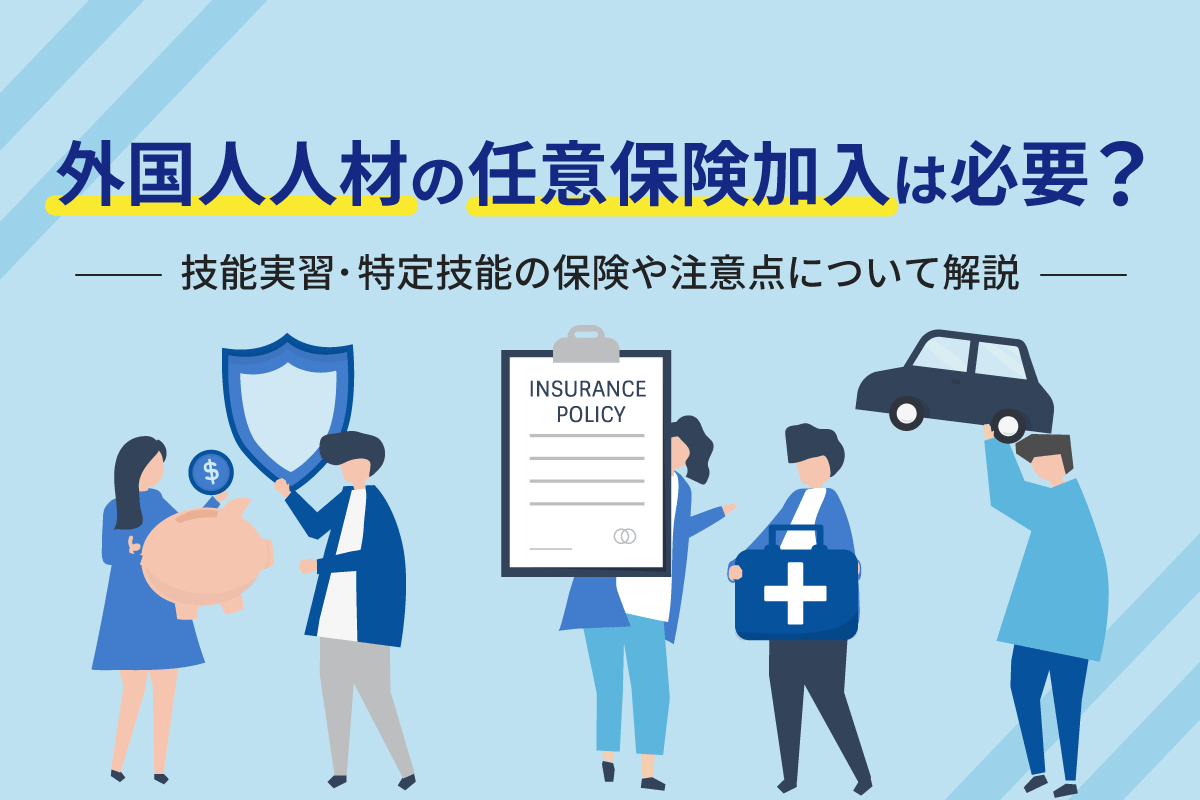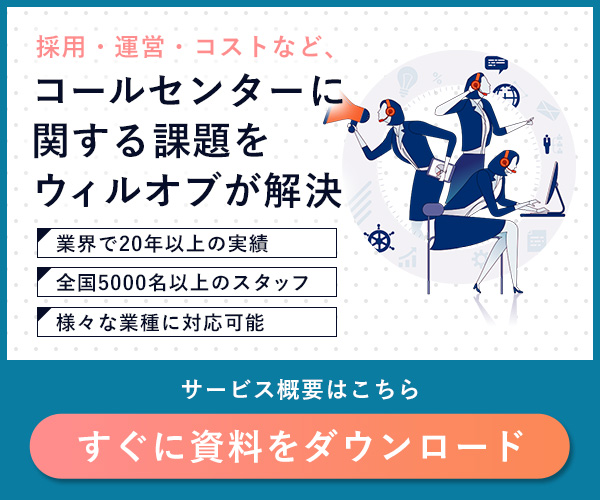コールセンターの離職率が高い6つの理由とは?対策方法も合わせて解説!
- アウトソーシング
- コールセンター
2025/06/24
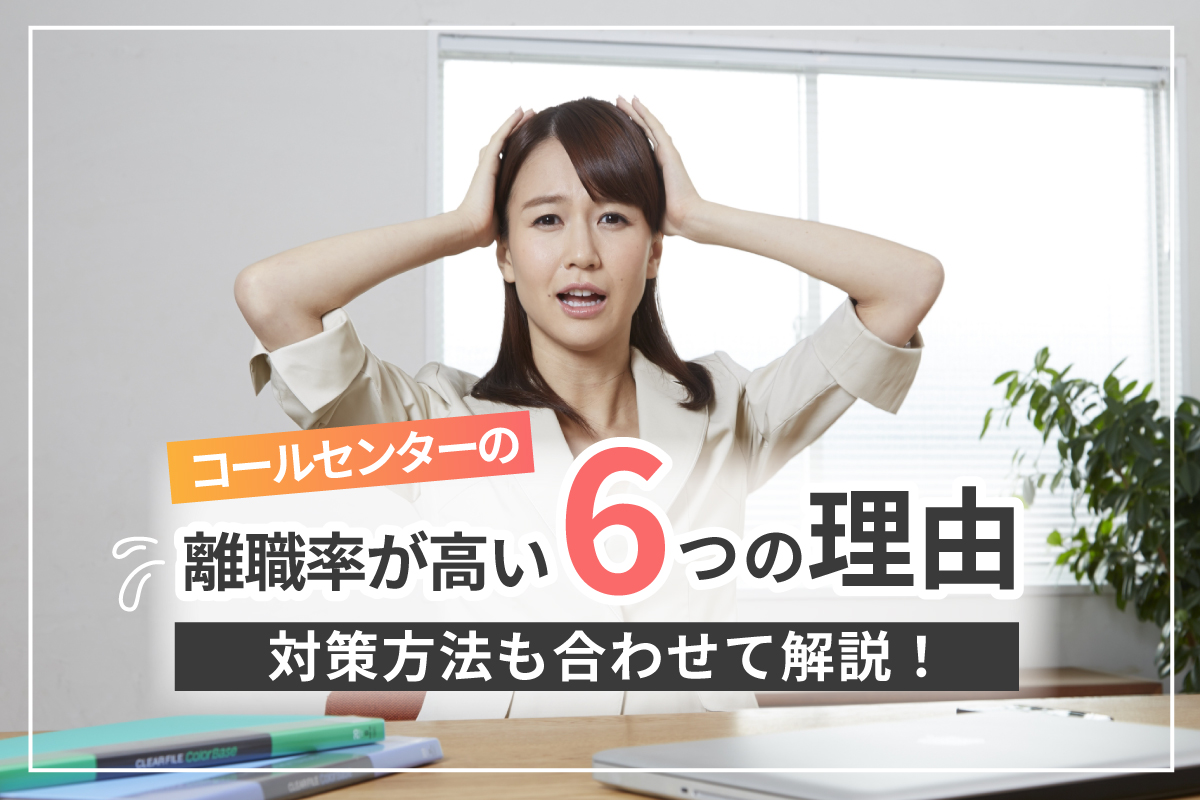
この記事でわかること
- コールセンターの離職率が高い理由
- 離職率の低いコールセンターの特徴と対策
- アウトソーシングで採用・育成コストを削減
コールセンターは離職率の高い職場といわれています。本記事では、コールセンターの離職率が高い理由と、離職率を下げる対策について解説します。
TOPICS
コールセンターの一般的な離職率

コールセンターの職場では、入社から1年以内に退職する人の割合が70%を超えるケースが、全体の約4分の1を占めるというデータがあります。
参考:月刊コールセンタージャパン
このような高い離職率は、人材の定着難や応対品質のばらつきといった問題を引き起こしやすく、組織運営上の大きな障壁となります。
しかし、反対に離職率を抑えることができれば、オペレーターの熟練度が高まり、質の高い応対を安定して提供できる環境が整います。経験豊富なスタッフが多く在籍していれば、顧客対応の精度も向上し、さまざまな問い合わせに柔軟かつ的確に応じることが可能となるでしょう。
コールセンター人材について課題をお持ちの方はこちらの申し込みフォームからお気軽にご相談ください。課題解決に向けて伴走いたします。
コールセンターの離職率が高くなる6つの要因
コールセンターにおける高い離職率は、多くの企業にとって深刻な課題となっています。
弊社では、多くの企業のご担当者と現場の課題について意見交換を重ねる中で、離職につながりやすい共通要素を抽出しました。
ここでは、その中でも特に影響が大きい6つの理由をご紹介します。
ウィルオブ・ワークは、コールセンターに特化した人材支援で、定着率の高い運営体制づくりをサポートしています。お気軽にご相談ください。
クレーム応対による心理的負担
顧客対応の現場では、厳しい口調や不満をぶつけられる場面が日常的に発生します。
インバウンド業務では、過度なクレームや理不尽な要求に対応し続けることで、オペレーターが心身ともに疲弊してしまうケースが少なくありません。「自分が責められている」と感じてしまい、強いストレスを抱えることもあります。
アウトバウンド業務においても、「興味がない」「忙しいからやめて」といった否定的な反応を日常的に受けるため、精神的な消耗が蓄積しやすい傾向にあります。
こうしたプレッシャーや感情的な負担が続くと、やがて心が限界を迎え、離職につながることがあります。特に、カスタマーハラスメントへの会社の対応が不十分な場合、スタッフの精神的な負担は一層大きくなります。
数値目標(ノルマ)へのプレッシャー
アウトバウンド型のコールセンターでは、営業目標や成績に関するノルマが設定されていることが一般的です。
しかし、営業電話は断られることが多く、思うように成果が出ないこともしばしば。努力しても数字が伸びない状況が続くと、自信をなくし、「この仕事は自分に向いていない」と感じて辞めてしまう人もいます。
数値目標(ノルマ)へのプレッシャー
アウトバウンド型のコールセンターでは、営業目標や成績に関するノルマが設定されていることが一般的です。
しかし、営業電話は断られることが多く、思うように成果が出ないこともしばしば。努力しても数字が伸びない状況が続くと、自信をなくし、「この仕事は自分に向いていない」と感じて辞めてしまう人もいます。
不十分な研修や支援体制
業務に必要な知識やスキルを十分に身につけるためには、初期研修やその後のフォロー体制が不可欠です。
しかし、教育制度が整っていない職場では、オペレーターが不安を抱えたまま実務に入ることになり、トラブルやミスが起こりやすくなります。
その結果、上司から叱責される、顧客からクレームを受けるといった経験を繰り返し、職場に対する不信感が高まり、退職の決断につながることがあります。
指示内容のばらつきによる混乱
現場では、スーパーバイザー(SV)などの管理者が業務指導を行いますが、担当者が変わるたびに指示の内容や方針が異なると、オペレーターは混乱してしまいます。
「研修で教わった通りにやったのに、別のSVからは違うと言われた」といった状況が続くと、何を信じて仕事をすればよいのかわからなくなり、不安や不満が蓄積していきます。こうした信頼関係の揺らぎが、離職の引き金となることもあります。
スキルが身につかない
コールセンターは未経験者でも始めやすい仕事ですが、その一方で、キャリア形成の面では課題もあります。
日々の業務がルーチンワークになりがちで、「このまま続けても成長を実感できない」と感じる人も少なくありません。長期間同じ業務を繰り返す中で、将来的なキャリアへの不安が芽生え、他の職種を目指して退職するケースも見られます。
人材育成・教育研修・業務効率化まで、一社ごとの課題に応じた最適なご提案をいたします。お気軽にご相談ください。
離職率が高い・低いコールセンターの違い

労働政策研究・研修機構の前浦穂高研究員による分析では、離職率が高い職場と低い職場にはそれぞれ一定の傾向が見られるものの、業種や年齢構成、または女性比率といった属性だけでは違いを説明しきれないことが明らかになっています。
参考:コールセンターの組織類型別分析
離職率が高くなりがちなコールセンターの特徴
離職者が多く出る傾向にあるコールセンターでは、正社員の給与水準が全体的に低いか、あるいは他部署と同程度である傾向が見受けられます。
精神的なプレッシャーが強く、業務負担も大きい職種でありながら、報酬面での差がなければ、働く意欲が維持しにくくなるのは当然といえるでしょう。
また、顕著な違いとは言えないまでも、「自分の裁量で動ける範囲が限られている職場」や「1日のコール数が非常に多い現場」では、退職率が高まる傾向も見られるようです。
業務の自由度が低い環境では、やらされ感が強まり、モチベーションが続きにくくなります。
離職率が低いコールセンターに見られる特徴
反対に、離職率の低いコールセンターにはいくつかの共通点があります。
まず、精神的な負荷の大きさを適切に評価し、給与が納得感のある水準に設定されている職場では、社員の離職率が低い傾向にあります。
さらに、業務の裁量がある程度与えられている環境では、働き手が自身の判断で柔軟に対応できるため、仕事への主体性が育ちやすくなります。初期段階で基礎的な研修をしっかりと行っておけば、日々の対応はある程度個人の裁量に任せることも可能です。
また、教育・研修制度が整っており、スキルアップを支援する体制がある職場では、長期的に働こうとする意欲が高まりやすくなります。しっかりとしたサポートがあることは、安心して働き続けられる理由のひとつとなるでしょう。
コールセンターの離職率を下げるための具体的な取り組み
コールセンター勤務者の退職理由や不満の声から、離職を防ぐための施策を見出すことができます。ここでは、離職につながりやすい要因に対応する形で、効果が期待できる6つの対策を紹介します。
精神的負担を和らげるには、報酬やメンタルケアが鍵
コールセンター業務において最大の課題は、精神的ストレスの大きさです。そのため、まずは給与や手当など金銭的な面での優遇措置を講じることが基本的な対策のひとつといえるでしょう。
ただし、経済的なサポートだけでは不十分です。上司やSV(スーパーバイザー)による定期的な面談や1on1の機会を設け、業務上の悩みやストレスを打ち明けられる環境を整えることも非常に重要です。
面談を通じて得られた現場の声や改善点は、チーム全体で共有し、再発防止や働きやすい職場づくりの材料として活用していくことが、離職率の低下につながります。
覚えなくてもいい仕組みづくり
オペレーターの業務負担を減らせるよう、極力、覚えなくてもよい仕組みづくりを推進しましょう。そのためには、お客さまに対応しながら参照できるテキスト作りが肝心です。
該当箇所をすぐに探し出せるよう、検索機能をアップさせたり、問い合わせの多い事柄を優先してテキストにのせたりするなどの工夫が考えられます。業務内容に合わせてどのような工夫ができるか、チームで話し合いが必要です。
ノルマの現実性を再検討する
成果を求めること自体は当然ですが、誰も達成できないような目標設定では、モチベーションが低下し、退職にもつながります。
ノルマが売上計画から逆算された数字であっても、実際の達成状況と乖離していないかを見直し、現実的にクリア可能な水準へ調整することが大切です。
まずは、これまでの実績データを分析し、「毎月どれくらい達成できているのか」を基準に、目標値を再設定しましょう。
新人には1on1型の手厚いフォローを
大人数を対象にした集合研修だけでは、個別の理解度に差が出やすく、新人の不安を払拭できない場合があります。
離職率の高さに悩んでいる場合は、先輩社員がマンツーマンで新人を指導する“1on1研修”の導入を検討しましょう。
とはいえ、通常業務と並行して指導するのは難しいため、最初のうちは新人が電話を取らず、先輩の対応をそばで観察する“シャドーイング”期間を設けたり、新人の対応時にすぐ横でサポートできる体制を整えたりすると安心感につながります。
指導の一貫性を保つための連携
「研修で教わったことと現場での指示が食い違う」といった不満は、意外と多く聞かれます。これはSV(スーパーバイザー)と研修担当者の間で指導内容の共有ができていないことが原因です。
SVは事前に研修資料を確認し、可能であれば研修に同席するなどして、実務での指導とのズレを解消しましょう。逆に、SV側からのフィードバックにより、研修内容自体に修正が必要な場合もあります。その際は速やかに改善することが重要です。
コールセンターで得られるスキルを明確化
「この仕事ではスキルアップできない」と感じて辞めていく人もいますが、実際には多くの能力が養われています。
たとえば、電話応対のマナー、聞く力(傾聴力)、的確に話をまとめるコミュニケーション能力、問題解決力など、他業種でも活かせるスキルが自然と身につきます。
これらのスキルが習得できる職場であることを、社内でも積極的に伝えることで、キャリア形成の意識を高め、離職防止につなげることができます。
「採用してもすぐ辞める」「SVの指導がバラバラ…」
そんな悩みを抱えるご担当者さまへ。課題解決に伴走いたします。お気軽にご相談ください。
外部委託による業務負担とコストの軽減
離職率を改善するには、報酬の見直しやメンタルサポートなど、多くの人的・金銭的リソースが必要です。
その負担を抑える手段として有効なのが、コールセンター業務のアウトソーシングです。
外部の専門業者に委託することで、採用・教育にかかるコストや労力を削減でき、自社スタッフはコア業務に専念しやすくなります。結果として、従業員の満足度向上や定着率改善にもつながります。
また、多くの委託型サービスでは、対応件数や業務量に応じた従量課金制が導入されているため、ムダな人員確保も不要になります。
コールセンターの内製と外注の違いについては「コールセンターの外注と内製の違いとは?」で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
▼関連記事
コールセンター委託会社7社比較!各社の特徴を解説
コールセンターを委託する際のポイントは?費用や選び方を解説
おわりに
コールセンターの人員は、多くの企業にとって事業成長に欠かせません。しかし、高い離職率のために常に人材コストを払わなければならない状況は、打開しなければなりません。
人材活用や育成についての方法について今一度課題の洗い出しからはじめていきましょう。
コールセンター業務の外注で、人材課題とコストを一挙解決!
採用・研修・マネジメントまで一括対応。「人が足りない」を根本から解決できるアウトソーシングサービスの詳細は資料にて。
ウィルオブ・ワークにお気軽にご相談ください。