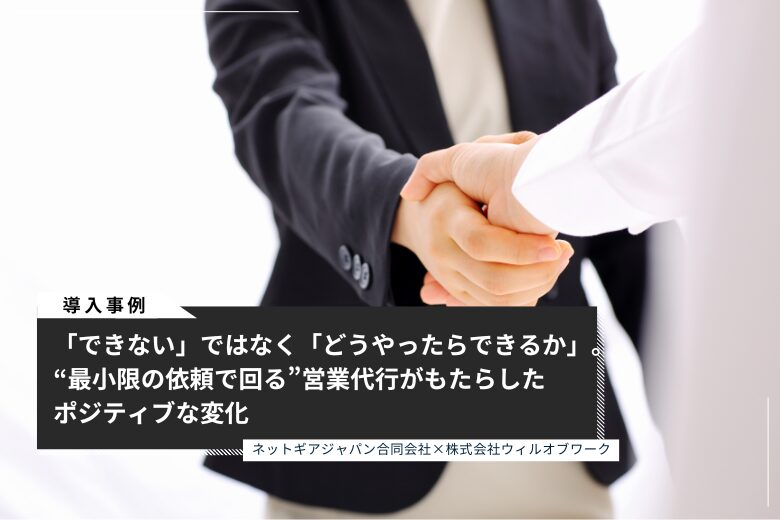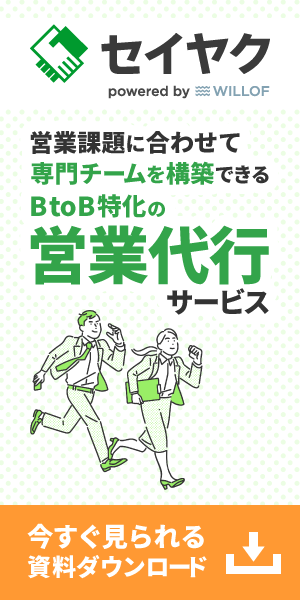カスタマーサクセス体制のつくり方|リソース不足でもできる実践ガイド
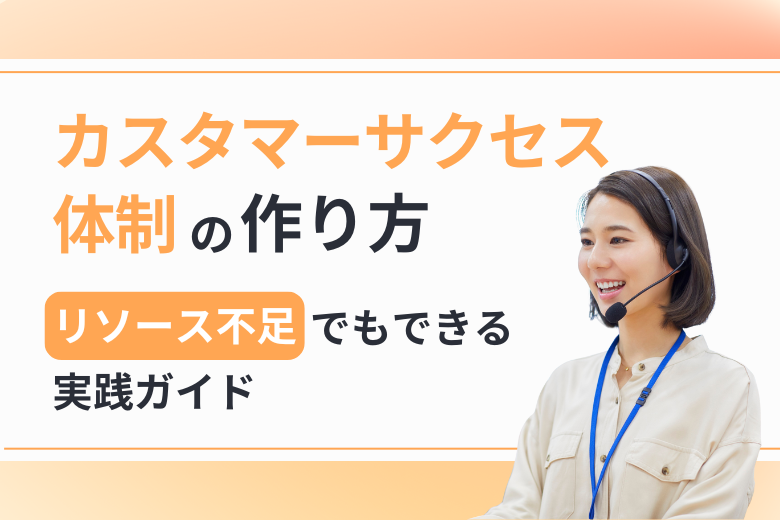
サブスクリプション型ビジネスが広がり、顧客の継続率が事業の成長スピードを大きく左右するようになりました。
特に継続利用を前提とするビジネスモデルでは、契約後の体験をどう設計し、顧客を成功へ導くかが収益そのものに直結するため、カスタマーサクセス(CS)体制の整備は欠かせない取り組みになりつつあります。
一方で、実際に体制を整えようとすると壁にぶつかる企業が少なくありません。
当社の調査では、65.3%の企業が営業リソース不足を抱え、38.0%が人員の不足を課題と回答しています。
加えて、39.7%が優秀な人材を確保できないことに不安を感じており、CS人材の採用難度も高いままです。
つまり、体制構築の重要性は理解しているが、実行に移しづらい状況が起きています。
本記事では、こうした制約がある環境でも無理なく始められるCS体制構築の方法を実例とともに整理。
段階的な進め方から失敗しやすいポイントまで、限られたリソースで成果を出すための考え方を解説します。
カスタマーサクセス体制の構築に課題を感じている方へ
専門人材が確保できない、担当者が不足して体制が進まない・・・。そんな課題は珍しくありません。『セイヤク』では、カスタマーサクセス代行を通じて、解約率改善やLTV向上を支援しています。
営業代行『セイヤク』の資料請求をする
なぜカスタマーサクセス体制が課題になるのか
企業の多くはCSの重要性を認識しつつも、「具体的なやり方が分からない」「人員を割けない」といった理由で立ち上げが停滞しがちです。
CSには専門性の異なる複数の役割が含まれるため、一定のスキルと時間の確保が欠かせません。
しかし、既存業務で手一杯の企業にとってはそのリソースを捻出することが難しく、結果として着手が遅れてしまうのです。
当社が実施した調査では、 38.0%が営業人員不足を課題と認識しており、 39.7%が優秀な人材の確保に不安を感じています。
この傾向は新規営業だけでなく、カスタマーサクセス領域にも直結します。
専門性の高い人材ほど採用難度が高く、育成にも時間がかかるため、そもそも体制を組むところまで辿り着けないケースも少なくありません。
とはいえ、継続利用を売上の基盤とするサブスクリプション型ビジネスでは、解約率とLTVが事業の成否を左右します。
いまや「新規を追うだけ」では成長が鈍化しやすく、既存顧客の成功体験づくりをどれだけ仕組み化できるかが、中長期成長の鍵となっています。
なぜCS体制は“思ったより難しい”と感じられるのか
カスタマーサクセス体制を立ち上げると、多くの企業が予想していなかった課題に直面します。
必要性は理解しているものの、実際の運用では「想像より複雑だった」「リソースが足りず理想の形に近づけない」といった声も珍しくありません。
どこでつまずきやすいのかを事前に把握しておくだけでも、立ち上げ後のやり直しを防ぎ、スムーズに体制を育てられます。
KPIを抱え込みすぎてしまう
CS立ち上げ初期は、成功させたい意欲が強いために指標を増やしがちです。
しかし、KPIが増えるほど活動の焦点がぼやけ、改善すべきポイントが見えにくくなります。
結果として、施策が分散し、運用のスピードが落ちることも少なくありません。
初期フェーズでは、事業にインパクトの大きい指標へ絞り込み、その他の項目は観測に留めるほうが運用は安定します。
計測環境が整わないまま走り出してしまう
ログが蓄積されない、利用状況を把握できないといった状態で運用を開始すると、活動の成果がどこに表れているのか判断できません。
データが見えないまま改善を続けると、施策が感覚頼りになり、効果検証もしづらくなります。
顧客データはサービス改善の源泉でもあるため、最低限の計測環境を整えておくことが、CS体制を機能させる前提条件になります。
対象顧客を広げすぎて崩れる
初期段階で「全顧客にCSを実施しよう」とすると、対応量が膨らみ、分析や改善に手が回らなくなる傾向があります。
結果的に、支援の質が薄くなり、成果を実感しにくい状態に陥りがちです。
まずは効果が出やすい顧客、改善インパクトの大きい顧客に絞り込み、支援を集中させるほうが初期成功をつかみやすくなります。
リソースの現実を無視して理想モデルに寄せすぎる
理想的なCSモデルを参考にすること自体は有益ですが、現実の人員やスキルと乖離した体制を無理に組もうとすると、運用が続かなくなる場合があります。
今あるリソースを起点に段階的に整える視点を持つことが、早く体制を整えるカギです。
段階的に進めるカスタマーサクセス体制の5ステップ
CS体制の構築を家づくりに例えると、基礎を固めずに内装を整えても、長期的に安定した運用は望めません。
重要なのは、土台を整え、徐々に機能を積み上げていくことです。
ここでは、立ち上げから運用までの基本ステップを紹介します。
ステップ1:課題整理と現状把握
初めに行うべきは、自社の課題と現状の棚卸しです。
既存顧客のデータ、売上計画、コスト構造、人員体制などを整理することで、どこから着手すべきかが明確になります。
リソース不足が本質的な課題なのか、プロセスが未整備なのか、もしくはノウハウが不足しているのか、原因を把握しておくことが次のステップにつながります。
ステップ2:優先度の高い顧客セグメントの選定
すべての顧客を対象にしないほうが、初期の成功率は高まります。
成果につながりやすい顧客、施策の影響が大きい顧客、あるいは活用状況によってチャーンリスクが高い顧客など、注力すべきセグメントを絞り込みましょう。
運用しながら精度を高めることもできますので、はじめは仮説ベースで問題ありません。
ステップ3:組織モデルの検討
自社の事業フェーズやプロダクトの複雑度に合わせて、適切な組織モデルを選定しましょう。
代表的なモデルは以下の通りです。
- オールラウンダー型:少人数で運営する企業に多く、CSが幅広い業務を担う
- セールス指向型:CSと営業が密に連携し、既存顧客の拡大を重視する構造
- 伴走型:顧客に深く入り込み、継続的に課題解決を行うモデル
- スペシャリスト型:CS内に専門チームを設け、分野ごとに高い専門性で支援する形
規模や商材によって適した形は変わるため、「自社の目的に合う体制かどうか」を基準に選ぶことが大切です。
ステップ4:KPI設計とプロセス定義
初期はKPIを増やしすぎないことが鉄則です。
事業へ直接インパクトがある指標に絞り、測定できる環境を整えたうえで運用しましょう。
同時に、オンボーディング・アダプション・活用促進・解約防止など、各フェーズで「何を成功とみなすのか」を明確に定義することも重要です。
これがチーム間の連携をスムーズにし、活動の質を安定させます。
ステップ5:小さく始めて、段階的に広げる
体制構築はいきなり完璧を目指さないことが重要です。
まずは1名からでも支援を開始し、運用の癖や改善ポイントを掴みながら、徐々に対象範囲を拡大するアプローチが現実的といえるでしょう。
成果を確認しつつ、段階的に人員や活動領域を増やすことで、無理のない体制が整います。
リソース不足下でも実践できるアプローチ
十分な人数がいなくても、工夫次第で効果的なCS体制の構築は可能です。
ここでは、実際に現場で多く採用されている手法を紹介します。
優先顧客に集中する運営
限られたリソースで最大成果を出すには、優先順位づけが欠かせません。
顧客の活用状況を把握するだけでも、改善余地の大きな顧客が見つかることがあります。
まずはそこに活動を集中させることで、短期的なチャーン防止にもつながるでしょう。
少人数から始めるスモールスタート
立ち上げ当初から大人数を配置する必要はありません。
事実、ECモール運営企業A社では、1人が約200店舗を担当しながらKPI管理や事例共有を行い、売上目標対比で最大120%を達成しました。
少人数でも運営可能であることを示す好例です。
外部委託(代行)の活用
専門人材を採用できない、早期に体制を整えたい、または内部のコストを抑えたい場合は、外部の専門チームを活用する選択肢も有効です。
代行企業を選ぶ際は、実績や商材理解の深さ、改善提案力、報連相、柔軟な対応力などを基準にすると失敗しにくくなります。
人材サービス企業B社では、営業リソース不足や解約防止体制の不備が課題でしたが、営業代行会社とともに新規開拓・顧客フォロー・解約防止施策を行ったことで、目標達成や解約率改善、LTV向上へとつながりました。
体制構築時に押さえておきたいコストとROI
カスタマーサクセス体制を整えるには、どうしても一定の投資が発生します。
人材の配置や育成にかかるコストだけでなく、活用状況を可視化するツール費用や、業務プロセスを設計・整理するための工数も必要です。
こうした要素を一度にまとめて整えるのではなく、段階的に投資していくことで、CS活動の再現性が上がり、継続率やLTVの改善にもつながりやすくなるでしょう。
体制をゼロから立ち上げる場合、投資対効果が見え始めるまでには、おおよそ半年〜1年ほどが必要です。
ただし、必要な期間は企業規模やプロダクトの複雑さによって大きく変わり、どれだけ早く改善サイクルを回せるか、どこまで定量的に検証できるかが、ROIを押し上げる鍵になります。
また、内部リソースだけで進めるか、外部の支援も組み合わせるかは状況次第です。
外部パートナーを活用する場合は、立ち上がりを加速できる反面、社内にどこまでナレッジを残すのかという観点も欠かせません。
いずれの選択肢を取るにしても、「どんな体制を目指すのか」「どの指標で回収を判断するのか」を先に言語化し、そこから逆算してコスト配分を決めていくことが、納得感のある投資判断につながります。
カスタマーサクセス体制構築のチェックリスト
カスタマーサクセスの立ち上げでは、複数の領域を同時並行で整理する必要があります。
どこから手をつけるべきか迷わないよう、体制構築の全体像を俯瞰できるチェックリストとしてまとめました。
初期フェーズの抜け漏れを防ぎ、段階的に体制を整えるための指標としてご活用ください。
- 課題整理:顧客情報、売上計画、コスト構造、人員体制の整理
- 組織モデルの選定:事業フェーズ・商材特性に合った体制を選ぶ
- KPI設計:初期は指標を絞り、測定可能な環境を整える
- リソース配分:優先顧客を定め、段階的に拡大する
- 外部活用:採用困難・立ち上げ急務の際に検討する
よくある質問(FAQ)
このセクションでは、カスタマーサクセスの体制構築を目指す企業からよくある質問に回答します。
Q1:少人数でも体制構築できますか?
A:可能です。優先度の高い顧客に集中し、スモールスタートで進めれば無理なく運用できます。
Q2:外部委託はどのタイミングで検討すべきですか?
A:専門人材の採用が難しいとき、早期に立ち上げたいとき、内部コストを抑えたいときが目安です。
Q3:体制構築にはどれくらいの期間が必要ですか?
A:規模によって異なりますが、基本的な体制は3〜6か月で整うことが多いです。
Q4:どの組織モデルが最適か判断できません
A:事業フェーズや商材の複雑さを基準に選びます。少人数ならオールラウンダー型、高単価・複雑商材なら伴走型、大規模組織ならスペシャリスト型が向いています。
Q5:KPIはどのように設定すべきですか?
A:初期は1〜2つに絞り、運用が安定してから段階的に指標を増やします。
まとめ
カスタマーサクセス体制の構築は、特定の企業だけが抱える課題ではなく、多くの事業が直面する共通テーマです。
必要性は理解していても、実際には「どこから手をつけるべきか」「人員やスキルをどう確保するのか」といった悩みが生まれやすく、思った以上に複雑さを感じる領域でもあります。
体制を固めるうえで重要なのは、理想像を一気に再現しようとするのではなく、現状を踏まえた段階的な設計です。
優先顧客を見極め、小さく成功体験を積み上げ、改善サイクルを回しながら体制を育てていくことで、限られたリソースでも継続率やLTVにポジティブな変化が生まれます。
自社だけで進めるか、外部の知見を部分的に取り入れるかはそれぞれですが、どちらにしても「目指す顧客体験を明確にし、そこから逆算して体制を組む」姿勢が、長期的に機能するCS体制への近道になります。
カスタマーサクセス体制の構築に課題を感じている方へ
専門人材の確保が難しい、リソース不足で進まない・・・。そんな場合はぜひお問い合わせください。『セイヤク』では、LTV向上や解約率改善に直結するCS代行支援が可能です。
営業代行『セイヤク』の資料請求をする

SalesMedia 編集部
SalesMediaの記事を制作・配信している編集部です。
営業支援に役立つ情報を発信していきます。