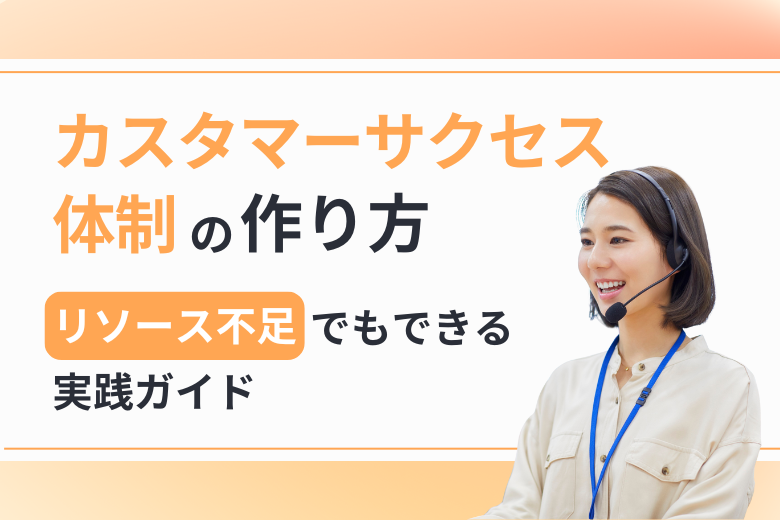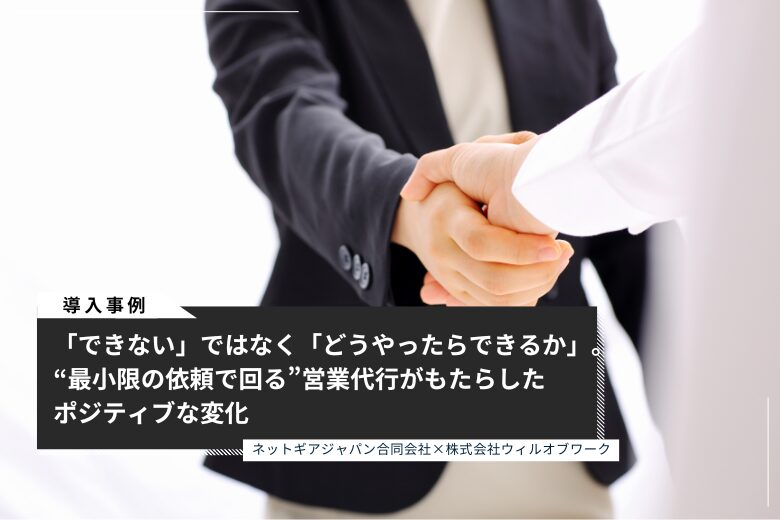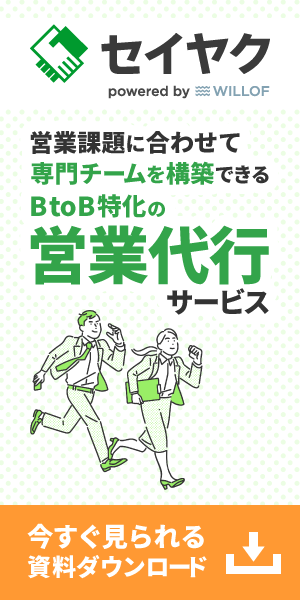カスタマーサクセスと営業の連携を強化する方法|仕組み・手順を徹底解説

営業が獲得した顧客の期待値をカスタマーサクセス側で正しくつかめていない。
部門ごとに顧客情報が分断されているせいで、アップセルやクロスセルのチャンスが目の前を通り過ぎている。
このように営業とカスタマーサクセス間の連携で悩みを抱える企業は少なくありません。
本記事では、営業とカスタマーサクセスがかみ合わない原因を整理したうえで、連携を強化するための具体的な仕組みづくりと実践手順をまとめて解説します。
カスタマーサクセスと営業の連携を強化したい、連携体制を構築したい方へ
専情報共有不足で連携がうまくいかない、部門間の連携を強化したいとお考えの方は、ぜひお問い合わせください。『セイヤク』では、営業代行とカスタマーサクセス代行の両方を提供し、一貫した連携体制の構築が可能です。
営業代行『セイヤク』の資料請求をする
カスタマーサクセスと営業の連携がうまくいかない理由
カスタマーサクセスと営業の連携が崩れると、顧客満足度がじわじわと低下し、やがて解約率の上昇となって表面化します。
これは営業が商談時に聞き取った期待値や背景情報が、カスタマーサクセス側に十分渡っていないことが多くの原因です。
また、顧客情報の管理が部門ごとに分かれている場合、アップセルやクロスセルの好機も拾いづらくなります。
こうした問題を解消するためには、一時的な改善ではなく、連携を前提にした体制を設計する必要があります。
具体的には、目的の共有、情報の一元管理、定期的なコミュニケーション機会の設計、KPIのそろえ方、ツール活用の方針といった要素をセットで整えていくことが重要です。
社内リソースだけでは整備しきれない場面では、営業代行やカスタマーサクセス代行といった外部リソースを組み合わせ、連携を意識した体制を構築する方法も選択肢のひとつといえるでしょう。
カスタマーサクセスと営業の連携が重要な理由
なぜここまでカスタマーサクセスと営業間の連携が重視されるのでしょうか。
背景には、営業体制そのものが抱える構造的な課題があります。
当社の調査では、営業リソースの充足感について「足りない」と回答した企業が65.2%にのぼりました
営業体制の課題としては「営業人員不足」が38.0%、「属人化でノウハウが蓄積されにくい」が23.2%と回答されています。
参考:営業に関する調査結果(データ)
人員が足りず、情報が属人化している状態のままでは、顧客情報の引き継ぎや部門間連携が滞りがちです。
この状況で営業とカスタマーサクセスの接続が弱いと、営業が獲得した顧客の期待値がカスタマーサクセスに伝わらず、契約後の体験ギャップが生まれ、結果として、満足度の低下や解約の増加につながりやすくなります。
カスタマーサクセスは本来、営業・マーケティング・サポートなど複数部門と接続するハブのような存在です。
特にBtoBのSaaSでは、導入から数ヶ月のあいだに成果を体感できなければ離脱リスクが一気に高まるとされており、初期フェーズの連携は事業継続に直結します。
カスタマーサクセスと営業の連携が不足すると、まず顧客の期待値と提供価値にズレが生まれやすくなり、導入後の満足度が下がって解約につながるリスクが高まります。
利用状況や課題感に基づくアップセル・クロスセルの好機もつかみにくくなるため、LTVの伸びも頭打ちに。
さらに、顧客情報が部門ごとに分断されたままだと、適切なタイミングで最適な提案を行う判断が難しくなり、売上機会そのものを取り逃しやすくなります。
こうした連鎖を防ぎ、顧客にとっての価値を一貫して届けるためにも、営業とカスタマーサクセスの連携は欠かせない取り組みです。
カスタマーサクセスと営業の連携における課題と失敗パターン
このセクションでは、連携を阻む要因をもう少し細かく見ていきましょう。
現場でよく聞かれる課題を整理すると、次のようなパターンが見えてきます。
情報共有不足
営業が把握している顧客の課題や意思決定プロセスが、カスタマーサクセス側に十分に伝わっていない。
逆に、利用状況や活用度、顧客から寄せられた細かな声が、営業に戻っていない。
こうした情報共有の不足は、部門間連携を阻むもっとも根本的な要因の一つです。
部門間の連携不足
営業とカスタマーサクセスがそれぞれの目標に追われ、別々のリズムで動いているケースも多く見られます。
定例ミーティングなどの接点が十分に設けられておらず、顧客の状況を共有する機会が限られていると、共通認識を持つことが難しくなるでしょう。
拠点分散による連携の難しさ
拠点が分かれているチームでは、物理的な距離が連携のハードルになることも。
例えば、カスタマーサクセスが名古屋、インサイドセールスが福岡、フィールドセールスが名古屋と大阪といった構成の場合、朝礼や夕礼以外に全員で顔を合わせる機会を作れず、情報共有が部分的になってしまうことがあります。
期待値の不一致
営業が商談段階で描いた成果イメージと、カスタマーサクセスが提供する支援内容にズレがあると、顧客の期待値は簡単に崩れます。
どこまでがサービス提供範囲なのか、いつどのような成果を目指すのかといったポイントを揃えないまま話が進むと、導入後に「聞いていた話と違う」という不満につながりやすくなります。
営業とカスタマーサクセスの連携を強化する手順
営業とカスタマーサクセスの連携を強化するには、個別の取り組みを積み上げるだけでなく、両部門が同じ基準で判断し、同じ情報をもとに動ける状態を整えることが欠かせません。
このセクションでは、連携を安定的に機能させるための具体的なステップを、実務で使いやすい形で整理します。
ステップ1:目的の共有と明確化
最初に取り組みたいのは、両部門が向かう方向をそろえることです。
顧客満足度の向上やLTVの最大化、解約率の低減といった共通目標を設定し、それぞれが同じ解釈で捉えられているかを確認します。
目的が共有されていると、顧客対応の優先順位を判断する場面でも迷いが生まれにくくなり、組織全体が一貫した動きを取りやすくなるでしょう。
ステップ2:情報の一元管理と共有
連携を阻む要因の多くは、顧客情報の散在にあります。
CRMやSFAを活用して商談履歴、問い合わせ内容、利用状況などを一か所にまとめることができれば、部門間の認識の差を縮められるでしょう。
加えて、議事録やミーティングの共有ルールを整えておくと、日々の動きや判断が自然と可視化され、属人化の防止にもつながります。
情報更新のルールまで決めておくと、管理が担当者頼みにならず安定した運用が可能になります。
ステップ3:定期的なコミュニケーションの実施
システム上の共有では見えない細かなニュアンスは、対話の場で補いましょう。
週次ミーティングを設け、顧客の状況や最近の相談内容、成功事例の共有などを行うことで、双方の視野がそろいやすくなります。
拠点が分かれているチームでは、オンライン会議や録画共有を組み合わせることで、物理的な距離による情報格差を最小限に抑えられます。
ステップ4:KPIの設定と評価制度の統一
営業とカスタマーサクセスが異なる指標で動いていると、どうしても目的のズレが生まれます。
架電数、商談数、受注率、継続率など、両部門が共通で追うKPIを設定し、数字の意味や背景になる行動まで共有する仕組みを整えることが大切です。
日次・週次・月次で進捗を振り返る運用を取り入れ、未達の理由を明確にしたうえで次のアクションにつなげる習慣をつくると、連携の質が継続的に高まります。
ステップ5:ツールの活用
連携を支える仕組みとしてツールの活用を検討するのもひとつの手です。
カスタマーサクセス専用のプラットフォームを利用すると、顧客の利用状況やヘルススコアをリアルタイムで把握でき、先回りしたフォローや提案がしやすくなります。
また、情報更新や共有のフローを明確にしておくことで、誰が関わっても同じ品質で顧客対応ができる状態を維持できます。
よくある質問(FAQ)
カスタマーサクセスと営業の連携に関して、現場から寄せられる質問と回答をまとめます。
Q1. カスタマーサクセスと営業の連携がうまくいかない理由は何ですか?
A. 典型的な理由としては、情報共有不足、部門間のコミュニケーション不足、期待値の不一致などが挙げられます。
当社の調査でも、営業体制の課題として「属人化でノウハウ蓄積されにくい」、「教育・育成リソース不足」、「営業戦略が整理されていない」といった回答が出ており、こうした土台の弱さが連携を妨げる要因になっています。
Q2. 連携強化の効果はどのくらいで現れますか?
A. 実施する施策や事業の性質によって幅はありますが、一般的には3〜6ヶ月ほどで変化を感じ始めるケースが多く見られます。
まずは定例ミーティングの設置やKPIの統一など、基礎的な取り組みから着手することで、段階的に改善効果を実感しやすくなります。
Q3. 小規模企業でも連携強化は可能ですか?
A. 可能です。むしろ少人数だからこそ、優先度の高い顧客セグメントに対象を絞り、情報共有の仕組みと定例のコミュニケーションだけでも整えると、連携効果を実感しやすくなります。
「小さく始めて大きく育てる」という考え方が有効です。
Q4. 外部リソースを活用した連携のメリットは何ですか?
A. 営業代行やカスタマーサクセス代行などの外部リソースを活用することで、専門性の高い人材を短期間で確保でき、連携体制の立ち上げや改善を効率的に進められます。
Q5. 連携強化のためのツールにはどんなものがありますか?
A. 代表的なものとして、CRM(顧客関係管理システム)、SFA(営業支援システム)、カスタマーサクセス専用のプラットフォームなどが挙げられます。
これらを活用することで、顧客情報の一元管理やリアルタイムでの情報共有がしやすくなります。
まとめ
カスタマーサクセスと営業の連携は、単に「仲良くする」ことではなく、共通の目的のもとで情報とプロセスをつなげる取り組みです。
目的の共有、情報の一元管理、定期的なコミュニケーション、KPIと評価軸の統一、ツールの活用という五つのポイントを押さえることで、連携は徐々に機能し始めます。
自社だけでの体制構築が難しい場合は、外部リソースの力も借りながら、段階的に仕組みを整えていくのも現実的な選択肢です。
連携が強化されることで、顧客満足度の向上、解約率の低下、アップセル・クロスセルの促進といった成果が期待でき、結果として事業全体の収益最大化にもつながっていきます。
カスタマーサクセスと営業の連携を強化したい、連携体制を構築したい方へ
専情報共有不足で連携がうまくいかない、部門間の連携を強化したいとお考えの方は、ぜひお問い合わせください。『セイヤク』では、営業代行とカスタマーサクセス代行の両方を提供し、一貫した連携体制の構築が可能です。
営業代行『セイヤク』の資料請求をする

SalesMedia 編集部
SalesMediaの記事を制作・配信している編集部です。
営業支援に役立つ情報を発信していきます。