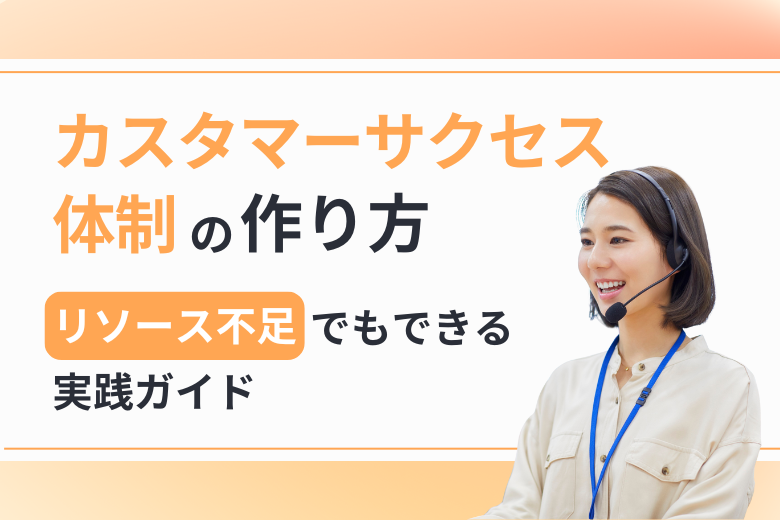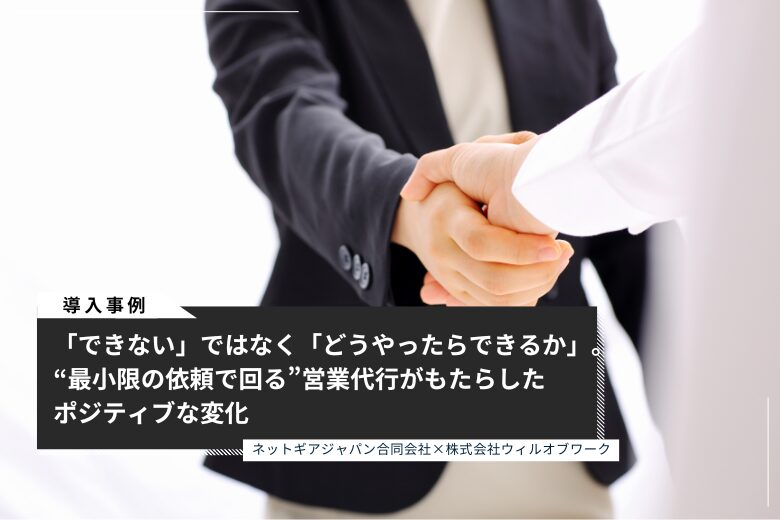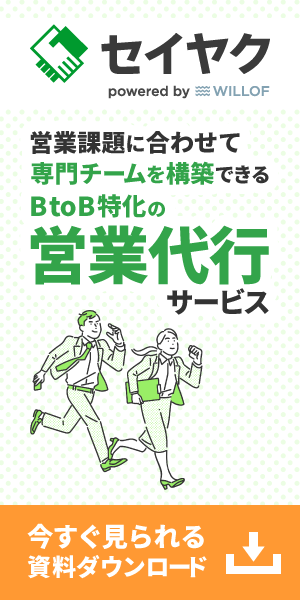カスタマーサクセスのオンボーディング強化の方法|課題と改善策を解説

契約が決まったあと、使い方の資料を送っただけでフォローが止まってしまう。
オンボーディングの重要性は理解しているのに、日々の業務に追われて後回しになってしまう。
カスタマーサクセスの現場では、このような悩みがよく挙がります。
カスタマーサクセスにおけるオンボーディングは、顧客がサービスの価値を実感し、長く使い続けてもらうための入り口となるプロセスです。
一方で、人員やノウハウが限られるなかで、どこまで設計すべきか判断に迷いやすい領域でもあります。
この記事では、オンボーディングの基本的な考え方から、具体的な手法、業界別の設計ポイント、実際の事例、改善ステップまでを紹介。
明日から現場で試せるヒントを軸にまとめていきます。
カスタマーサクセスオンボーディングの進め方が分からない、リソース不足で後回しになってしまう方へ
オンボーディングの重要性は理解しているものの、具体的な設計や運用に課題を感じている場合は、ぜひお問い合わせください。『セイヤク』では、カスタマーサクセス代行の実績をもとに、オンボーディング体制の構築と運用を支援します。
営業代行『セイヤク』の資料請求をする
カスタマーサクセスオンボーディングでよくある悩み
「どのタイミングで何を案内するべきか、流れが整理しきれていない」
「担当者の人数が足りず、きめ細かなフォローまで手が回らない」
「業界や顧客ごとに事情が違い、標準的な型ができていない」
オンボーディングに課題を抱える企業からは、上記のような声をよく伺います。
このような状態が続くと、顧客はサービスの価値を感じる前に利用をやめてしまいがちです。
本来オンボーディングは、契約から本格活用までの道のりを一緒に描き、最初の成功体験をつくるためのプロセスです。
この記事では、こうした悩みを整理しながら、どのように設計し直せばよいかを順番に見ていきます。
カスタマーサクセスオンボーディング成功のポイント
オンボーディングをきちんと機能させるうえで、軸になる考え方はシンプルです。
まずは「顧客が何のためにサービスを導入したのか」「どの段階でどの状態になっていれば成功といえるのか」 を明確にし、段階的な支援を組み立てていきます。
具体的には、ウェルカムメールでの期待値整理、段階的な操作ガイド、セミナーや研修、多面的なサポート窓口、利用状況に応じたフォロー。
この五つの要素を、自社のリソースと顧客特性に合わせて組み合わせていくイメージです。
すべてを自社だけで賄うのが難しい場合は、カスタマーサクセスやオンボーディングに知見を持つ外部パートナーと役割を分担しながら、段階的に体制を整えるというのも選択肢のひとつです。
カスタマーサクセスにおけるオンボーディングとは
カスタマーサクセスにおけるオンボーディングとは、新規顧客が契約後にサービスをスムーズに使い始め、早い段階で価値を実感できる状態までを支援する初期プロセスを指します。
単なる操作説明ではなく、顧客の業務の中でどう活用していくかを一緒に描き、最初の成功体験をつくるところまでを含めた取り組みです。
カスタマーサクセス全体の流れは、一般的に次の四つのフェーズに分けて考えられます。
- オンボーディング:初期設定や使い始めの支援
- アダプション:日常業務への定着と活用範囲の拡大
- エクスパンション:アップセルやクロスセルによる利用拡大
- プロダクトフィードバック:利用状況をもとにした改善の提案
この中でもオンボーディングは、最初の印象を決める重要なタイミングであり、ここで「このサービスなら成果が出そうだ」と感じてもらえるかどうかが、その後の継続利用やプラン拡大に直結します。
カスタマーサクセス全体の役割や位置づけについて確認したい方は、次の記事もご覧ください。
【2025版】カスタマーサクセスとは?定義や役割・導入メリットを解説
オンボーディングが重要な理由と市場実態
近年オンボーディングが注目されている背景には、企業の収益構造が大きく変化してきたことがあります。
サブスクリプション型のビジネスが広がり、単発の売上よりも継続利用による積み上げが、事業の安定性を左右する時代になりました。
継続率が下がれば、売上の土台が揺らぎます。
どれだけ長く、どれだけ深くサービスを使い続けてもらえるかを示すLTV(顧客生涯価値)が重視されるのは、この構造変化が理由です。
一方で、現場では体制面の限界も見えてきています。
当社の調査では、営業リソースが「足りていない」と答えた企業が65.3%(かなり足りない22.6%+やや足りない42.6%)、営業体制の課題として「営業人員不足」を挙げた企業が38.0%、「教育・育成リソース不足」が22.6%という結果が出ました。
参考:営業代行サービスに関するアンケート調査
とはいえ、初期段階での価値実感が弱ければ継続利用につながらないため、この工程を疎かにすることはできません。
このような背景から、限られた体制でもオンボーディングの質をどう担保するかが、今後の事業運営において重要なテーマとなっています。
オンボーディング失敗の典型パターンと課題
オンボーディングがうまく機能していないと、初期解約の増加や、サービスへの不信感につながるなど、さまざまな影響が生じます。
ここでは、現場でよく見られる失敗パターンを三つに整理します。
失敗パターン1:放置による機会損失
最も多いのが、契約後に資料やマニュアルだけ渡して、そのまま様子を見るケースです。
顧客は操作方法や業務への組み込み方で迷っているにもかかわらず、相談のきっかけがないまま時間だけが過ぎていきます。
結果として、価値を感じる前に利用が止まり、「結局使いこなせなかった」という印象を持たれたまま解約に至ることもあります。
契約直後の数週間に、こちらから能動的にコンタクトを取る仕組みを持てているかどうかが、一つの分岐点になるといえるでしょう。
失敗パターン2:画一的な対応
業界や企業規模、導入目的が異なるにもかかわらず、すべての顧客に同じマニュアルや動画だけを案内してしまうケースです。
とくにBtoB領域では、「どの部署で」「どの業務フローの中で」使うのかによって、説明の順番や強調すべきポイントが大きく変わります。
画一的なコンテンツだけでは、顧客の現場感に合わず、自社向きではないと判断されてしまう可能性があるため、業界や利用シーンごとにパターンを分ける工夫が必要です。
失敗パターン3:リソース不足による支援体制の不備
人員不足や兼務状態により、オンボーディングに十分な時間を割けないケースも代表的な課題です。
前述の調査でもあるように、営業人員不足や教育・育成リソース不足を課題とする企業は多く存在します。
人員不足により、フィールドセールスがオンボーディングまで兼務しているという企業も多く「どうしても抜け漏れや着手の遅れが出てしまう」といった声も少なくありません。
オンボーディングの重要性は認識していても、日々の営業活動と両立しきれない体制設計になっていることが、失敗の背景にあるケースも多いと言えるでしょう。
効果的なカスタマーサクセスオンボーディングの5つの手法
オンボーディングを行き当たりばったりではなく「仕組み」として回していくために、押さえておきたい五つの手法を整理します。
オンボーディングは、顧客がサービスという船に乗り込み、目的地に向けて漕ぎ出すまでを一緒に準備するイメージです。
操作の説明だけでなく、どの順番で何を体験してもらうかを組み立てていくことで、成果につながる速度が変わってきます。
1. ウェルカムメールによる期待値整理
契約直後に送るウェルカムメールは、単なる挨拶ではなく、これからの付き合い方を示す役割を持ちます。
サービスで実現できること、最初に取り組んでほしいステップ、困ったときの相談窓口などを簡潔にまとめて案内すると、顧客側も次に何をすればよいかイメージしやすくなるでしょう。
初月や初回の節目として「最初の30日でここまで進めることを目標にしましょう」といった到達点を共有しておくと、顧客と提供側の認識をそろえやすくなります。
2. 段階的な操作ガイドの提供
機能を一覧で説明するよりも、「まずこれだけ理解しておけば日常業務で使い始められる」という最小セットから案内する方が定着しやすくなります。
チュートリアル動画や画面キャプチャ付きガイドを用意し、基礎編・応用編・活用編のように段階を分けると、顧客は自分のペースで学習できるでしょう。
一度で全てを伝えようとせず、最初の一歩を小さく設計することが、つまずきを減らすポイントです。
3. セミナーや研修による活用イメージの共有
基本操作に慣れてきた顧客に対しては、業務での活用方法に焦点を当てたセミナーや研修が有効です。
他社の事例や、よくある業務フローに沿った使い方を紹介すると、現場でのイメージが湧きやすくなります。
新入社員が基礎から実務へと段階的にステップアップするように、顧客にも基礎、応用、実践と段階を踏んでもらうイメージでコンテンツを構成すると、無理なく活用が広がっていきます。
4. 多面的なサポート体制の整備
オンボーディング期間中は、顧客からの質問や不安が出やすいタイミングです。
問い合わせのハードルを下げるために、複数の相談チャネルを用意しておくと安心感が生まれます。
軽い確認にはチャットやメールで素早く対応し、設定や業務フローの見直しのようなテーマはオンラインミーティングで深く話すなど、内容に応じて窓口を使い分けられる状態が理想です。
加えて、よくある質問を整理したFAQやヘルプページを用意しておくと、顧客自身で解決できる場面も増えていきます。
5. 進捗の見える化とフォロー
顧客がどの程度利用を進めているか、どの機能で止まりがちかを把握しながら、必要なタイミングで声をかけていくことも重要です。
ログイン状況や機能利用の履歴を確認し、一定期間動きがない顧客にはリマインドを入れるなど、シンプルな仕組みでも効果があります。
大切なのは、監視しているという印象ではなく「困ったときにすぐ相談できる存在」として認識してもらうことです。
こうした日々の関わりが、信頼関係の土台になります。
業界別オンボーディング設計のポイント
オンボーディングの基本的な考え方は共通ですが、業界や商材特性によって、設計の重点は変わります。代表的な業界ごとのポイントを整理します。
IT・SaaS業界での設計ポイント
ITやSaaSでは、機能が多く設定も複雑になりやすいため、導入初期の技術的なハードルをどこまで下げられるかが鍵になります。
管理者向けに初期設定や権限設計を扱うハンズオン研修を実施し、その後に一般ユーザー向けの操作トレーニングを行う二段階構成が有効でしょう。
また、本番環境とは別に検証環境を用意し、実データを扱う前に試せる場をつくっておくと、顧客側も安心して導入を進めやすくなります。
導入初期は技術サポートチームとの連携を密にし、問い合わせがあった際にすぐ対応できる体制を示しておくことも大切です。
教育業界での特殊事情
教育業界では、教職員、生徒や学生、保護者といった複数の立場の利用者が関わるため、それぞれに合わせた説明やサポートが必要になります。
さらに、年度や学期といったタイミングに合わせた導入計画も欠かせません。
一度に全学年へ導入するのではなく、一部のクラスや学年で試験運用を行い、その結果を踏まえて段階的に広げていく方が、現場の負担を抑えやすくなります。
教育業界の方からは、教育分野に詳しい営業人材が不足しており、未経験の人材だけでは成果が出にくいという声も聞かれるため、 業界特有の事情を理解した人材をどこまで配置できるかが、オンボーディングの成否に直結しやすいと言えるでしょう。
その他業界での考慮点
EC事業では、セール時期やイベントと重なると、教育やフォローの時間が取りづらくなるため、繁忙期を避けた導入スケジュールの設計が重要です。
実店舗など他チャネルとの連携も発生しやすい業界のため、関係部署を巻き込んだオンボーディング設計が求められます。
金融業界では、セキュリティやコンプライアンスに対する不安をどのように解消するかが大きなテーマに。
法令対応や情報管理の体制を丁寧に説明し、安心して利用できることを示すことが欠かせません。
医療やヘルスケアの領域では、個人情報保護や医療関連の規制に沿った運用が必須です。
既存の業務フローとの整合性を意識しながら、現場の負荷を抑えた導入ステップを設計していく必要があります。
いずれの業界でも、画一的なオンボーディングではなく、業界特性や顧客の事情を踏まえた調整を加えられるかどうかが、成果に直結します。
オンボーディング改善の実践手順
このセクションでは、オンボーディングを改善する具体的な手順を、4つのステップに分けて解説します。
STEP1: 現状分析
最初に行いたいのは、現在のオンボーディングの流れを可視化することです。
契約からどのタイミングで何を案内しているのか、どこで利用が止まりやすいのかを整理しましょう。
解約率や継続率といった数値に加えて、サポートへの問い合わせ内容や顧客インタビューなどを通じて、「どこで困っていたのか」「何があれば続けられたのか」といった具体的な声を集めると、課題の輪郭が見えやすくなります。
STEP2: 課題の特定と優先順位付け
現状を整理したうえで、改善すべきポイントを洗い出し、優先順位を決めます。
影響度と実行のしやすさの両方を軸にしながら、すぐに着手できるものと、中長期で取り組むものを分けていきましょう。
例えば、ウェルカムメールの文面改善やFAQの整理は、短期間で取り組みやすいテーマですが、専任チームの立ち上げや1on1研修体制の構築は、時間とリソースをかけて計画的に進める必要があります。
短期と長期の施策を組み合わせることで、改善を止めずに前に進めるポイントです。
STEP3: 改善施策の実施
優先順位が決まったら、具体的な施策に落とし込みます。
導入初期の離脱が目立つ場合は、初回ログイン後のガイドや、最初に達成してほしいゴールを整理するところから着手するとよいかもしれません。
使い方に関する相談が多いのであれば、操作動画の整備や、検索しやすいヘルプページの拡充が候補になります。
顧客との接点不足が課題であれば、定期的なチェックインミーティングを設定し、困りごとを早めに拾える仕組みをつくることも有効です。
STEP4: 効果測定と継続改善
施策を実行した後は、必ず効果測定のフェーズを設けます。
解約率、利用継続率、初回利用までの期間、サポート問い合わせ件数の推移などを定期的に確認し、どの施策がどの程度効いているのかを把握しましょう。
一度つくったオンボーディングを固定化してしまうのではなく、数値と現場の声をもとに少しずつ調整を重ねていくことで、自社の顧客に合った形に育てていくことができます。
オンボーディング業務の効率化と外部委託
オンボーディングの重要性を理解していても、自社の人員だけで全てを担おうとすると負荷が高くなり、細かなフォローが継続しないこともあります。
そうした状況で検討されるのが、外部委託の活用です。
内製化の限界と課題
CSチームの人数が限られていたり、求められるスキルを持つ人材を社内で確保しきれなかったりする場合、オンボーディング体制の内製化には難しさが伴います。
新規顧客が増えるほど一件あたりにかけられる時間が減り、結果的に支援の質が不安定になることも珍しくありません。
また、特定の担当者にノウハウが偏ると、その人の異動や退職が大きなリスクになることも。
業界特有の知識が必要な領域では、担当者の育成にも時間とコストがかかり、事業の成長スピードと人材育成のスピードが合わなくなることもあります。
外部委託のメリット
こうした課題に対し、カスタマーサクセスやオンボーディングに特化した外部パートナーを活用することで、必要なスキルや体制を短期間で取り入れられる場合があります。
オンボーディングには、顧客心理の理解、業界知識、コミュニケーション力、データの読み取りなど、多面的な能力が必要です。
すでにその領域で経験を積んだチームを活用できれば、自社で一から育成するよりも早く、一定の品質に到達しやすくなるでしょう。
また、繁忙期や新規顧客の急増時にリソースを柔軟に増やせる点もメリットです。
社内の固定人員だけでは吸収しきれない需要の波を、外部チームで補うことができます。
委託時の注意点
外部委託を検討する際には、自社のサービスや商材をどこまで深く理解してもらえるか、顧客情報の取り扱いが適切か、といった点を事前に確認しておくことが大切です。
あわせて、委託開始後に「どの指標を成果として見るのか」「どの頻度でレポートや振り返りを行うのか」を最初に決めておくと、双方で認識がずれにくく、改善サイクルも回しやすくなります。
当社の調査では、営業代行などの活用にあたって「成果への不安」を抱える企業が18.5%、「連携面への心配」がある企業が17.6%という結果が出ています。
こうした不安を前提として、成果指標や報告体制をあらかじめすり合わせておくことが、委託を成功させるうえでの重要なポイントといえるでしょう。
いきなり大きな範囲を任せるのではなく、まずは限定した業務や一部の顧客セグメントから試し、効果を確認しながら徐々に委託範囲を広げていく進め方をとると、リスクを抑えつつノウハウも蓄積しやすくなります。
よくある質問(FAQ)
オンボーディングに関して、現場からよく挙がる質問とその考え方の一例をまとめます。
Q1. オンボーディング期間はどの程度が適切ですか?
A. 商材や業界によって最適な期間は変わりますが、目安としては30日から90日程度で設計されることが多いです。
大切なのは期間そのものではなく、その間にどこまでの状態を目標とするかを決め、顧客が価値を実感できるところまで支援を続けることです。
教育業界のように、もともとの営業サイクルが長い分野では、より長いオンボーディング期間が必要になる場合もあります。
Q2. 効果測定はどのような指標で行えばよいでしょうか?
A. 解約率(チャーンレート)、利用継続率、顧客満足度、初回利用までの期間などが代表的な指標です。
加えて、サポート問い合わせ件数や主要機能の利用率の変化を追うことで、オンボーディング施策の影響をより立体的に把握できます。
単一の指標だけではなく、複数の指標を組み合わせて評価することで、偏りのなく効果を測定することが可能です。
Q3. 外部委託を検討する際の判断基準は何ですか?
A. 社内リソースの状況、求められる専門性のレベル、コストとスピードのバランス、事業の成長ステージなどが判断材料になります。
外部委託の利用にあたっては、成果や連携面の不安を感じる企業も多いため、委託範囲や成果の見方を事前にすり合わせておくことが重要です。
Q4. 業界経験のない担当者でもオンボーディングは可能ですか?
A. 実施自体は可能ですが、業界知識の習得や顧客理解の深掘りに、一定の時間と意識的な学習が必要です。
専門用語や業務フローを押さえたうえで、顧客の課題や背景に耳を傾ける姿勢が求められます。
教育業界のように専門性が高く、長期的な関係づくりが必要な分野では、業界経験者が関わった方がスムーズに進む場面もあります。
Q5. 小規模企業でも効果的なオンボーディングは実現できますか?
A. 規模が小さい企業でも、工夫次第で十分実現可能です。
むしろ、顧客との距離が近く、柔軟に対応しやすいという利点があります。
限られた人数で運用する場合は、テンプレートや自動化ツールを活用して標準部分を効率化し、要所で1on1のフォローを行うなど、リソースのかけ方にメリハリをつけることがポイントです。
まとめ
カスタマーサクセスにおけるオンボーディングは、顧客がサービスの価値を実感し、長期的な関係へとつながっていく入り口となるプロセスです。
複数チャネルのサポート体制と、利用状況に応じたフォローを組み合わせることで、初期のつまずきを減らし、解約の防止や継続利用の促進につなげやすくなります。
さらに、業界特性や顧客の事情を踏まえてオンボーディングを設計することで「自社向けの支援」と感じてもらいやすくなります。
社内リソースだけで体制構築が難しい場合は、外部パートナーと役割を分担しながら、無理のない形で仕組み化を進めることも選択肢の一つです。
カスタマーサクセスオンボーディングの進め方が分からない、リソース不足で後回しになってしまう方へ
オンボーディングの重要性は理解しているものの、具体的な設計や運用に課題を感じている場合は、ぜひお問い合わせください。『セイヤク』では、カスタマーサクセス代行の実績をもとに、オンボーディング体制の構築と運用を支援します。
営業代行『セイヤク』の資料請求をする

SalesMedia 編集部
SalesMediaの記事を制作・配信している編集部です。
営業支援に役立つ情報を発信していきます。